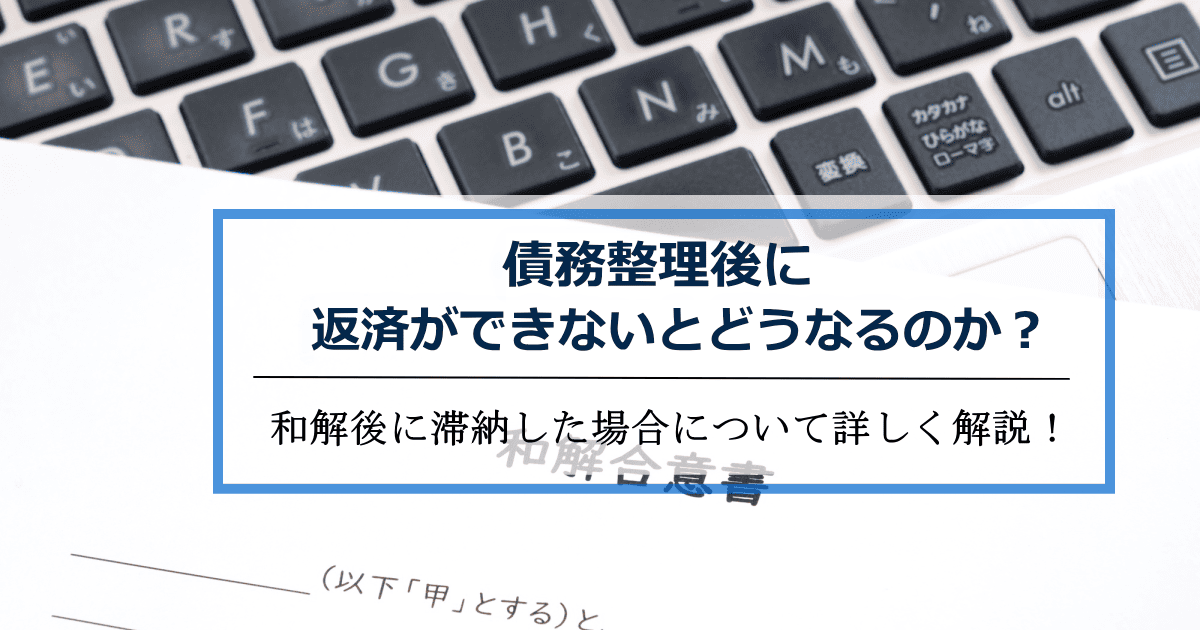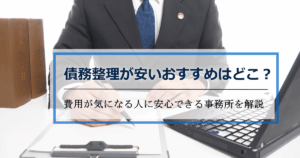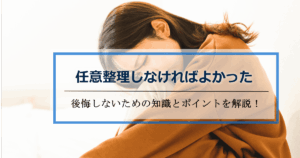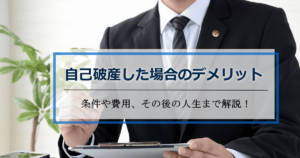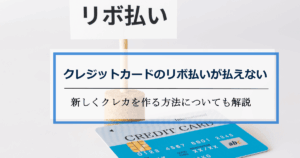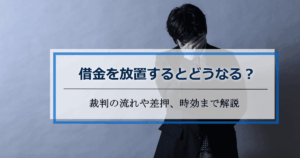債務整理には「任意整理」「個人再生」「自己破産」という3つの主な手続きがあります。どの手続きを選んだとしても、借金の返済負担を軽減できるという点で大きなメリットがあります。
しかし、「手続き後に返済を続けていけるかどうか」は、また別の問題です。実際に、債務整理後に以下のような悩みを抱えてしまう人も少なくありません。
「任意整理をしたけど、返済がきつくて払えない…」 「個人再生で再スタートしたのに、また滞納してしまった…」 「支払えないまま放置していたら、どうなるんだろう…?」
債務整理後に返済ができなくなった場合、手続きの種類によってリスクや影響も異なります。たとえば、任意整理後に滞納すれば、再び督促や差押えに発展する恐れがあります。個人再生では再生計画が取り消されてしまうかもしれません。
本記事では、債務整理後に支払えなくなってしまった場合のリスクや対処法について詳しく解説しています。今まさに滞納してしまっている人や、これからの支払いに不安を感じている人は、ぜひ参考にしてください。
債務整理後に滞納してしまった場合に起こるリスク

債務整理が完了したあとも債務が残り、支払いが継続するケースがあります。もし、債務整理後の残債を支払えなかった場合は、それまでに成立していた和解案や再生計画案が取り消され、残債の一括請求される可能性があります。
まずは、債務整理のうち「任意整理」「個人再生」「自己破産」それぞれで滞納した場合のリスクについて詳しく解説します。
任意整理の和解内容が無効になる可能性
任意整理で和解したあとに滞納した場合は、成立した和解案が無効となり、残債の一括請求される可能性があります。
そもそも、任意整理は債権者(お金を貸している側)と行われる交渉によって成立します。原則、利息のみをカットして元金のみを3年〜5年で完済する和解案を提示し、債権者からの同意を得られれば交渉が成立します。
基本的には元金はかならず残ります。しかし、和解成立後に元金の支払いが難しくなり、滞納してしまうケースも少なくありません。
和解成立時に提示される和解案には「◯回以上の滞納で一括請求を行う」といった記載があるはずです。そのため、和解案に記載されている通り、複数回の滞納で一括請求されてしまう可能性があるため注意しなければいけません。
個人再生の再生計画が取り消されるリスク
個人再生による再生計画認可決定後に滞納をした場合は、再生計画案が取り消されてしまう可能性があります。
個人再生は、住宅ローン以外の債務を大幅に減額し、残債を原則3年〜5年程度で支払い、完済を目指す債務整理手続きです。個人再生もかならず残債が発生する債務整理手続きであるため、再生計画認可決定後に「支払いができない……」といった状況に陥ってしまう人も少なくありません。
個人再生の場合は、「ハードシップ免責」や「再生計画の変更」といった選択肢があります。しかし、これらのことを行わずに滞納をしてしまうと、再生計画認可決定が取り消される可能性があります。
再生計画認可決定が取り消されてしまうと、多額のお金を支払って行った個人再生という手続き自体が無効となります。つまり、個人再生手続き前の状態になり、減額される前の債務を請求されてしまうのです。
認可決定後の滞納は「1回だけでも再生計画認可決定取り消しの可能性がある」という点に注意しなければいけません。実務上、1回の滞納で再生計画認可決定取り消しの可能性は低いものの、ゼロではありません。
自己破産後でも支払わなければならない債務に注意
自己破産の場合は、金融機関等からの借入すべてが対象となるため、基本的に「滞納してしまった……」といった状況は起こり得ません。しかし、自己破産をした場合であっても、「非免責債権」と呼ばれる債権は免責できません。
たとえば、税金や養育費、損害賠償金等は免責できないため、免責許可決定を受けた後であっても支払い義務が残ります。万が一、これらの支払いを滞納してしまった場合は、給与や預貯金等の財産を差し押さえられる可能性があるため注意しましょう。
債務整理後に支払えないときの対処法

債務整理をしても残債が発生するうえ、返済期間は3年〜5年程度と長期にわたります。そのため、返済中に失業や入院等で返済が困難になる可能性は十分に考えられます。
万が一、債務整理後に支払いが難しくなった場合は、以下の対処法を検討しましょう。
・債務整理を依頼した専門家に再依頼する
・家計を見直して支出を抑える
・公的支援制度の利用を検討する
・最終手段として、自己破産を検討する
次に、債務整理後に返済が難しくなった場合の対処法について詳しく解説します。
債務整理を依頼した専門家に再相談する

前に債務整理の依頼をした専門家に改めて、借金相談をしてみましょう。同じ専門家に相談をすることで、過去の履歴が残っているため、スムーズに話を進められる点がメリットです。
初めに相談をした専門家と別の人へ相談をすると、初めからすべてを説明しなければいけないため、スムーズに手続きを進められない可能性があります。また、専門家へ再相談をすることで、以下の対処法を検討・実行してもらえるでしょう。
| 債務整理 | 対処法 |
|---|---|
| 任意整理 | 改めて債権者と交渉を行う |
| 個人再生 | ・ハードシップ免責の検討 ・再生計画の変更 |
任意整理の場合、債権者(お金を貸している側)との交渉で和解が成立します。初回の任意整理で和解が成立していることから推察すると、元金のみを概ね3年〜5年程度かけて完済する和解案に債務者・債権者双方が同意しているはずです。
しかし、債務者であるあなたが和解案通りの返済ができない状況にあると推察できます。この場合、再度、債権者側と交渉を行って返済計画の見直しができる可能性があります。
任意整理は、あくまでも債権者側と行われる「交渉」であるため、1回目よりも厳しい状況です。しかし、1回目の任意整理成立後に遅滞なく返済をしていた場合は、2回目であっても柔軟に対応してもらえる可能性が高いです。
そのため、まずは初回相談をした専門家へ再相談をしたうえで返済計画の見直しを検討してみると良いでしょう。
個人再生の場合は、ハードシップ免責の検討もしくは再生計画の変更を検討することとなります。いずれの場合も、専門家によるサポートが必要であるため、前回相談した専門家へ再相談されることをおすすめします。
ハードシップ免責とは、認可された再生計画案通りに返済を続けていたものの、債務者に責任のない事情(不可抗力)によって返済が困難になった場合に利用できます。ハードシップ免責が認められた場合、残債は免責(支払い義務の免除)となります。
なお、ハードシップ免責が認められるためには、以下の要件を満たしていなければいけません。
・債務者に責任のない事情で返済困難になった場合
・3/4以上の返済が完了していること
・ハードシップ免責の決定が債権者の一般の利益に反しないこと
・再生計画案の変更をしても返済困難であること、もしくは再生計画案の変更が困難であること
ハードシップ免責における「債務者に責任のない事情」とは、たとえば長期入院や勤務先の倒産、リストラ等が該当します。個別事案ごとに判断されるため、まずは専門家へ相談をしてみましょう。
個人再生は、原則、減額された残債を3年〜5年かけて完済を目指す債務整理手続きです。途中で返済が難しくなった場合は、改めて再生計画の変更・調整を行える可能性があります。これを「再生計画の変更」と言います。最長で2年まで延長可能です。
専門家への再相談費用

専門家への再相談費用は、改めて行う債務整理手続きによって異なります。再度任意整理を行う場合や、任意整理から個人再生・自己破産を行う場合など、さまざまなパターンが考えられますが、再度であることを理由に費用が安くなったり高額になったりはしません。
費用相場は以下のとおりです。
| 債務整理 | 弁護士 | 司法書士 |
|---|---|---|
| 任意整理 | 3万円(着手金)+成功報酬(減額できた金額の10%が相場) | 3万円〜5万円 |
| 個人再生 | 50万円〜80万円 | 30万円〜40万円 |
| 自己破産 | 30万円〜60万円 | 20万円〜30万円 |
なお、個人再生におけるハードシップ免責や再生計画の変更を行う場合は、以下のとおりです。
| ハードシップ免責 | ・印紙代:600円〜1,000円 ・専門家費用:5万円〜15万円(専門家による) |
|---|---|
| 再生計画の変更 | 30万円〜80万円(個人再生と同等) |
家計を見直して支出を抑える

現在の家計状況を把握し、可能な限り支出を抑えたうえで返済費用を捻出する方法もあります。家計収支の改善は誰でもすぐに始められます。
まずは、収入と支出のそれぞれをすべて洗い出し、「見える化」することから始めてみましょう。すべてを可視化することによって、不要な支出が発見できます。発見できた支出を抑え、今後、無理なく返済をできるかどうか?を確認してみましょう。
家計収支を改善してもなお、返済が厳しい場合は早期に弁護士や司法書士への相談が必要な状況です。ためらわずにすぐに相談しましょう。
公的支援制度の利用も視野に入れる

失業や収入減少など、さまざまな事情で借金の返済が難しい場合は、公的支援制度の活用を検討してみましょう。
公的支援制度を大きく分けると以下の種類があります。
・総合支援資金
・福祉資金
・教育支援資金
・不動産担保型生活資金
借入の目的等によって利用できる支援制度は異なります。基本的には、「総合支援資金」と呼ばれる支援制度を利用することになるでしょう。本支援制度は「生活支援費」「一時生活再建費」といった名目で、1世帯あたり15万円〜20万円もしくは60万円までの借入が可能です。
さまざまな事情で債務整理後に支払い困難状況に陥ってしまう人がいます。状況次第では、上記支援制度を利用できる可能性があるため、検討されてみてはいかがでしょうか。
債務整理を行った人は個人信用情報に「異動情報」が掲載されるため、数年間は新たな借入等が難しくなります。しかし、公的支援制度は営利を目的とした金融機関ではないため、債務整理を行った人でも利用できます。
最終手段として自己破産を検討する

最終手段として、自己破産を検討する方法があります。任意整理や個人再生は、少なからず残債が発生し、支払いを継続しなければいけません。万が一、任意整理や個人再生後に支払いが困難になった場合は、一括請求等のリスクが発生するため注意しなければいけません。
また、再度任意整理をしたり個人再生をしたりしようとした場合は、交渉が難しくなります。再度和解が成立したとしても、その後にまた支払いが困難になってしまうことがあるかもしれません。
さまざまなことを考慮すると、「思い切って自己破産をする」という選択を検討しても良いのではないでしょうか。自己破産をすることで、非免責債権を除くすべての債務が免責となります。
非免責債権とは、養育費や損害賠償金、税金等の租税公課等、免責するに相応しくない債権を指します。これらの債権は、自己破産をしても免責にはなりません。
自己破産を検討する際の注意点
自己破産を検討する場合は、以下のことに注意してください。
・家族・会社に知られる可能性が高い
・一定以上の財産処分が前提
・免責不許可自由に該当する場合は免責許可がおりない
任意整理は家族や会社に知られることなく手続きを進められます。個人再生も、家族に知られる可能性はあっても、会社に知られる可能性は低いです。しかし、自己破産は家族・会社ともに知られてしまう可能性が高いため注意しなければいけません。
そして、自己破産を行う場合は、一定以上の財産を処分しなければいけません。たとえば、任意整理や個人再生の場合は住宅を残しておけますが、自己破産は住宅も処分対象となります。そのため、とくに住宅ローンを抱えている人は慎重に判断する必要があります。
自己破産には「免責不許可事由」というものがあります。免責不許可事由に該当する場合は、原則破産手続きによる免責許可決定を受けられません。たとえば、ギャンブルによる借金や過度な浪費の場合は免責不許可事由に該当します。
ただし、免責不許可事由に該当する場合であっても、裁判官の判断で免責許可決定が下される可能性があり、「裁量免責」と呼びます。
裁量免責を受けられるかどうかは、裁判官の裁量に委ねられていますが、まずは専門家への相談を検討されてみてはいかがでしょうか。
債務整理後に再相談をしても問題はない

前回、債務整理によって借金を減額したにも関わらず、再度支払い不能になり、再相談を検討している人は以下のような悩み・不安を抱えているのではないでしょうか。
「再相談でダメな人と思われるのではないだろうか?」「再相談をしても良いのだろうか?」「怒られたり、不利になったいりするのではないだろうか?」
上記のような悩み・不安を感じることは自然なことです。しかし、悩んでいても現況が改善するわけではありません。
次に債務整理後に再相談をしても問題ない理由について解説しますので、上記のような悩み・不安を抱えている人はぜひ参考にしてください。
再相談に不安を感じるのは自然なこと

再相談をする際は、さまざまな悩み・不安を抱えていることでしょう。「初回相談よりもハードルが高い」そう感じている人も多いのではないでしょうか。
「一回債務整理したのに、再相談をしたら怒られるのではないか」「本当に自分が情けない」このように思い悩み、苦しんでいるのではないでしょうか。こういった悩みや不安があるのは当然のことです。
1回目の債務整理で借金を減額し、多くの人は和解案や再生計画案に従って「今度こそしっかり返済していこう」そう誓ったことでしょう。
しかし、返済期間は3年〜5年と長期間にわたります。この期間に病気や怪我による長期入院、収入減少や大きな出費、失業等さまざまなことが起こり得ます。初回債務整理時は「大丈夫」「支払える」と思っていても、将来的に何が起こるかは誰にもわかりません。
不安を感じることは自然なことですが、不安なまま何もしなければ状況は悪化していくだけです。「不安だけど相談をする」その一歩が、今後の生活再建のスタートになるでしょう。安心して相談をしてください。
専門家は再相談でも親身に対応してくれる

過去に債務整理をした経験がある人でも、安心して専門家へ相談をしてください。債務整理の相談回数に関わらず、専門家は親身になって相談に乗ってくれます。
再相談を検討している人の多くは、さまざまな事情を抱えています。たとえ、同じ失敗であっても、債務者であるあなたのことを責める専門家はいません。なぜなら、責めたところで何も変わらないからです。専門家の職務は、「相談者の利益を最優先に考えること」です。
たとえば、1回目の債務整理の原因がギャンブルで、債務整理後に再度ギャンブルで借金を作ってしまい、返済が困難になったとしましょう。このような状況であっても、誰も債務者であるあなたを責めることはしません。
あなたの利益を最優先に考えたとき、責めるのではなく親身になって話を聞き、同じ失敗を繰り返さないためにはどうすれば良いか?を一緒に考えてくれます。債務整理はもちろんのこと、別の支援(ギャンブル依存症治療等)の提案も行ってくれるでしょう。
不安や悩みがあるのは当然です。しかし、専門家は債務者の利益を最優先に考え、親身になって話を聞いてくれるため安心して相談してください。
早期の再相談はメリットが多い

債務整理後の支払いが困難である場合、早期に再相談をすることで多くのメリットがあります。具体的には、以下のような点が挙げられます。
・現況を把握したうえで対処できる
・状況が悪化する前に対処できる
・対処方法の選択肢が増える
たとえば、「支払いが厳しい」と思った時点で早期に相談をしてもらえれば、滞納する前に対応できるため、債権者(お金を貸している側)との交渉がスムーズにいく可能性が高まります。
また、早期に対応できれば対応方法の選択肢が増えます。改めて任意整理をしたり、個人再生であれば、債権者と交渉をして返済期間を延長してもらったりできるかもしれません。
「自己破産を避けたい」と考えている人は、できるだけ早めに相談をすることで、さまざまな選択肢を検討できます。
そして、早期の再相談によって状況が悪化する前に対応できるため、精神衛生的にも良いです。滞納してしまえば、毎日の電話、督促状や一括請求の郵送物送付等が届き始めるでしょう。そうすると、債務者であるあなたの精神衛生にも問題が発生します。
早期に相談し、状況が悪化する前に対応できれば精神衛生面で見ても効果的であり、冷静に物事を判断できます。
債務整理後の支払いができないときにあるよくある質問

債務整理後の支払いができない時によくある質問を以下のとおり解説します。
- 債務整理後に滞納したらすぐに差し押さえられますか?
- 支払いを再開すれば和解は継続されますか?
- 債務整理再交渉は自分でもできますか?
- 新たな借金をしてしまったけど、また整理できますか?
- 相談にはお金がかかる?無料の相談窓口はありますか?
Q.債務整理後に滞納したらすぐに差し押さえられますか?
A.すぐには差し押さえられません。
財産を差押するためには、債権者(お金を貸した側)が「強制執行の申立て」を行わなければいけません。では、債権者が強制執行の申立てをした場合、直ちに差押が可能なのか?といえば、そうではありません。
実際に強制執行を行うためには、以下の手順を踏まなければいけません。
- 【債権者】支払督促の申立て
- 【裁判所】支払督促の発付・支払督促正本の送達
- 【債権者】仮執行宣言の申立て
- 【裁判所】仮執行宣言の発付・仮執行宣言付支払督促正本の送達
- 仮執行宣言付支払督促の確定
- 【債権者】強制執行の申立て
大まかな流れは上記のとおりです。初めに、債権者が裁判所に対して「支払督促の申立て」を行います。その後、書類に不備がなければ債務者に支払督促正本が送達されます。
強制執行における支払督促状は、債権者が独自に送付する書類ではなく裁判所が発付するものでなければいけません。つまり、裁判所から「督促状」が届いた場合は、強制執行手続きに移行されたと考えたほうが良いです。
債務者は、裁判所から届く支払督促状に対して2週間以内に異議申し立てができます。異議申し立ては、「一括請求は無理なので分割払いで支払いたい」など、交渉手段としても活用できます。
支払督促状の受領から2週間以内に異議申し立てが行われなかった場合は、債権者が仮執行宣言の申立てを行わなければいけません。書類等に不備がなければ、裁判所が「仮執行宣言付支払督促」を発付し、債務者に送達します。
債務者は、仮執行宣言付支払督促を受領してから2週間以内に異議申し立てを行えます。仮執行宣言付支払督促における異議申し立ても支払督促同様に、「支払いが厳しい」等の交渉する意思がある場合にも行えるため覚えておきましょう。
もし、仮執行宣言付支払督促から2週間経過しても異議申し立てが行われなかった場合は、確定します。確定した場合、債権者は強制執行の申立てを行い、実際に強制執行(差し押さえ)ができる状況となる流れです。
上記のとおり、債権者が「財産を差し押さえよう」と考え、実際に手続きを開始したとしても直ちに差し押さえられることはありません。また、債務者に対しては督促状送達時と仮執行宣言付支払督促の発付・送達時に2度のチャンスが与えられます。
遅くとも、仮執行宣言付支払督促が発付・送達された時点で異議申し立てを行うことで、強制執行を回避できる可能性が高いです。不安な場合は、弁護士等の専門家へ相談をしましょう。
Q.支払いを再開すれば和解は継続されますか?
A.和解案や再生計画案によって異なります。
任意整理による和解案の場合は、「◯回以上の滞納で一括請求を行う」等の記載があります。そのため、支払いを再開したとしても滞納が発生した場合は、和解案による効果が失効する可能性があります。
再生計画案の場合は、1度の滞納であっても再生計画案が失効する可能性があるため注意しなければいけません。
もし、支払いが遅れそうな場合はそのことが分かった時点で早期に債権者へ連絡をしましょう。とくに債務整理後は「信頼関係」が何よりも大事です。前もって連絡することで、信頼関係が継続でき、柔軟に対応してもらえる可能性が高いです。
Q.債務整理の再交渉は自分でもできますか?
A.可能ですがおすすめはできません。
債務整理の再交渉は自分でも行えます。しかし、弁護士等の専門家へ依頼した場合と比較して、交渉が難航するケースが多いです。弁護士は交渉の専門家でもあるため、代理してもらったほうが良いでしょう。
Q.新たな借金をしてしまったけど、また整理できますか?
A.債務整理後に新たな借金を抱えた場合でも、債務整理は可能です。
債務整理に回数制限はないため、何度でもできます。ただし、改めて自己破産を検討している人は注意が必要です。もし、「7年以内」に免責許可決定を受けている場合は、再度の自己破産はできません。
なぜなら、免責不許可事由に該当するためです。借金の事情次第では、裁量免責が認められる可能性があるものの、短期間で何度も自己破産を繰り返している場合は、心象も悪くなるため注意しましょう。
Q.相談にはお金がかかりますか?無料の相談窓口はありますか?
A.初回相談料は無料である事務所が多いです。
債務整理の初回相談を無料としている事務所が多いです。ただし、債務整理を実際に依頼した場合は、別途費用が発生します。費用相場は以下のとおりです。
| 債務整理 | 弁護士 | 司法書士 |
|---|---|---|
| 任意整理 | 3万円(着手金)+成功報酬(減額できた金額の10%が相場) | 3万円〜5万円 |
| 個人再生 | 50万円〜80万円 | 30万円〜40万円 |
| 自己破産 | 30万円〜60万円 | 20万円〜30万円 |
債務整理後に支払えないとどうなる?のまとめ
今回は、債務整理後に支払い困難になった場合の対処法について解説しました。
債務整理をしたあとでも、さまざまな事情で支払いが難しくなってしまうことは珍しくありません。病気や怪我による長期入院、失業や収入減少など、誰にでも起こり得る理由で「払えない」「支払えない」状況に陥る可能性があります。
しかし、滞納が続いてしまうと、和解案や再生計画案の失効や財産の差し押さえといった深刻なリスクが発生します。
任意整理では、滞納が続けば和解が無効となり、元の借金に利息を加えた金額を一括請求されるかもしれません。個人再生や自己破産でも、履行テストや免責に影響し、せっかくの手続きが水の泡になるケースがあります。
そのため、支払いが困難になった時点で、早めに対処することが重要です。
具体的な対処法としては、まず債権者や依頼した司法書士・弁護士に連絡し、状況を正直に伝えることが第一歩となります。家計の見直しや収入の確保に努めるのも有効ですが、すでに滞納してしまった場合は、自力での対応が難しいこともあります。そのようなときは、再度の債務整理や他の救済策を含め、専門家に相談するのが現実的な選択肢です。
債務整理後に滞納してしまったからといって、すべてが終わるわけではありません。むしろ、早い段階で動き出すことで、被害や不利益を最小限に抑えることができます。
一人で抱え込まず、まずは信頼できる法律の専門家に相談してみましょう。相談は無料で受け付けている事務所も多いため、「どうしたらいいかわからない」と思ったら、迷わず一歩を踏み出してみてください。
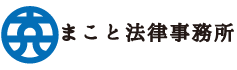
当事務所では法律のプロとして、専門知識を活かした問題解決を行っています。勝ち負けだけではなく、先を見据えた真の解決をご提案しています。
おひとりで悩まずに、まずはお気軽にお問合せください。