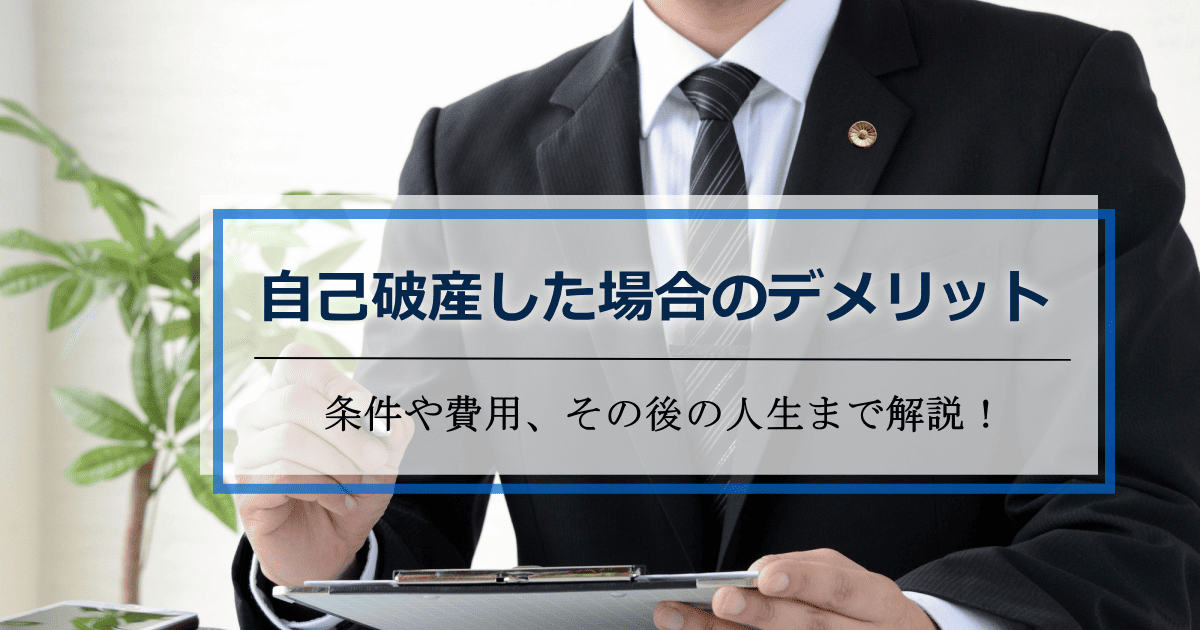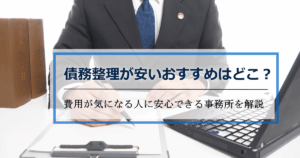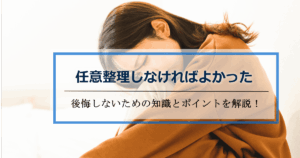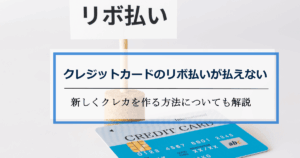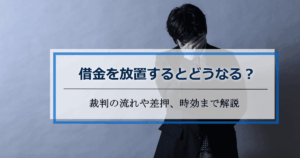多額の借金を抱えた場合、地道に返済する方法もありますが思い切って自己破産をする選択肢もあります。
自己破産と聞くと、「財産を処分しなければいけない」「ローンが組めなくなる」といったデメリットばかりが頭に浮かびますが詳細についてはよく理解されていないケースも多いようです。
そこで本記事は自己破産のデメリットや費用について、また「自己破産をしたあとの人生がどう変わるのか」について徹底解説したいと思います。
自己破産すると変わる事と変わらない事

自己破産をしてしまうと、これまでの生活が180度変わってしまうのではないかと思う人もいるでしょう。
たしかに自己破産をすると不動産などを処分する必要があるため、生活環境は多少なりとも変化します。ただ、変化がある一方で、自己破産をしても普段の生活には支障をきたさないこともたくさんあります。
まずは、自己破産をすると身の回りのどんな点が変わるのか詳しく解説していきます。
自己破産を含む債務整理が得意な無料相談の事務所一覧
| 項目/順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
|---|---|---|---|---|
| 商品名 | ひばり法律事務所 | 弁護士法人・響 | アース法律事務所 | ホワイトリーガル |
| おすすめ度 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.8 |
| 特徴 | ・相談何度でも無料 ・着手金分割OK | ・相談料0円 ・費用分割払い可能 | ・元裁判官の弁護士事務所 ・初回相談無料 | ・債務整理の実績多数 ・相談、着手金0円 |
| 任意整理 | ・着手金22,000円/1社 ・報酬金22,000円/1社 ・減額報酬金:11% ・実費5,500円/1社 | ・着手金55,000円~ ・解決報酬金11,000円~ ・減額報酬金:減額分の11% | ・着手金22,000円/1社 ・解決報酬金22,000円/1社 ・減額報酬金:10%相当 | ・着手金0円 ・手続き費用:22,000円 |
| 個人再生 | ・着手金33万円~ ・報酬金22万円~ | ・着手金33万円~ ・報酬金22万円~ (住宅有は33万円~) | ・着手金33万円~ (住宅ローン特例の場合は44万円~) ・報酬金22万円~ | 要相談 |
| 自己破産 | ・着手金22万円~ ・報酬金22万円~ | ・着手金33万円~ ・報酬金22万円~ | ・着手金22万円~ | ・着手金0円 ・手続き費用:165,000円 ・裁判所費用:15,000円前後 |
| 完済過払い | ・着手金0円 ・報酬金0円~ ・成功報酬:回収金の22%(訴訟の場合は27.5%) | ・着手金0円 ・解決報酬金22万円 ・過払報酬金:返還額の22%(訴訟の場合27.5%) | 要相談 (報酬金:返還額の20%~) | 要相談 |
| 全国対応 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
| 公式リンク | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
※金額はすべて税込み表示
弁護士法人ひばり法律事務所

ひばり法律事務所は借金問題の相談は何度でも無料ですので、すぐに依頼をしなくても不安が解消するまで相談することが可能です。また任意整理、個人再生、自己破産等の債務整理の着手金と成功報酬が安いので安心して任せることができます。
- 債務整理の着手金、成功報酬が安くて安心
- 家族に内緒で債務整理することもできる
- 借金問題の相談は何度でも無料!弁護士依頼費用の分割も対応が可能
ひばり法律事務所ではプライバシー厳守を徹底しているため、家族に内緒で債務整理をすることも可能です。弁護士事務所無記名の封筒での郵送や、郵便局留めの指定などにも対応してもらえます。
また、全国対応の弁護士事務所なので遠方に住んでいても特に問題はありません。
【任意整理+過払い金請求をしたケース】
借金残高305万円→110万円、さらに過払い金50万円が返還された。
【個人再生で持ち家を手放さずに解決したケース】
月々の返済額19.5万円→10.5万円まで減額+自宅を手放さず解決。
債務整理の費用
| 任意整理 | 個人再生 | 自己破産 | 過払い金 | |
|---|---|---|---|---|
| 着手金 | 22,000円/1社につき | 330,000円~ | 220,000円~ | 0円 |
| 報酬金 | 22,000円/1社につき | 220,000円~ | 220,000円~ | 0円~ |
| その他費用 | 減額報酬11% | 若干の諸費用あり | 若干の諸費用あり | 回収金の22%が成功報酬 |
弁護士法人・響

弁護士法人響の債務整理サポートチームには下記の特徴があります。
- ご依頼後速やかに介入通知を送るので借金の督促を止めることが可能
- 全国対応で24時間、365日相談受付
- 弁護士相談料0円!弁護士費用の分割払いも可能
弁護士法人響は、全国対応で24時間・365日相談受付が可能になっています。相談料は0円で弁護士費用の分割払いも可能なため、まずは無料・匿名でできる減額相談を行うことをおすすめします。(弁護事務所名:士法人・響 所属:第二東京弁護士会所属)
弁護士法人響の無料減額相談>>アース法律事務所

アース法律事務所は、元裁判官の弁護士が借金問題を解決してくれる人気の弁護士事務所です。
- 借金問題3,500件超の実績
- 元裁判官の弁護士が借金相談に応じることが可能
- 遠方でも問題なし!全国対応可能の弁護士事務所
債務整理実績3,500件超のアース法律事務所は、債務整理案件に強い弁護士事務所です。初回相談無料で全国対応なので気軽に相談することができます。
アース法律事務所の借金無料相談>>自己破産すると変わる7つの事

まず自己破産をして自分の生活に影響が出る点としては、以下の7つのことがあげられます。
- 不動産や一定以上の預貯金は処分が必要
- 一定期間、銀行や消費者金融からの借入れができない
- クレジットカードの新規契約や利用継続に影響がでる(一定期間のみ)
- 弁護士や司法書士、宅地建物取引士など一部の仕事に就けなくなる(復権まで)
- 賃貸マンションの契約(金融系の保証会社を利用する場合・一定期間のみ)
- 再度の自己破産や個人再生ができなくなる
- 破産手続き中の引っ越しに制限がかかる
いくつかの影響があるなかで、しばらくのあいだ新規ローンやクレジットカードの契約ができない点は生活に影響が出るかもしれません。
持ち家を持っている場合は手放す必要がありますので、子どもがいる場合は転校がともない面倒なことが起こる可能性も出てきます。
不動産や一定以上の預貯金は処分が必要

自己破産をする場合は一定額以上の財産は処分し、お金にかえて債権者に分配しなければいけません。
自己破産の決定を受けて免責許可が出ると、借金の返済義務はなくなります。ただ、お金を貸した金融機関からすると、自己破産されると大きな損害を被るでしょう。
そのため、少しでも財産がある場合は財産を処分して現金にかえたあと債権者への返済金に充当されます。
以下は福岡地裁で決められた「自己破産をするときに処分対象外になる財産」の一覧ですが、以下に該当しない財産については処分しなければいけないことになります。
たとえば、「100万円以上の現金や20万円以上の預貯金」は処分しなければいけません。
福岡地裁の例/換価基準について
第1 換価等をしない財産
破産者が有する次の(1)から(9)の財産については、破産手続における換価又は取立て(以下「換価等」という。)をしない。ただし、破産管財人の意見を聴いて相当と認める場合は、法定自由財産でないものについて、換価等をすることができる。
(1)99万円に満つるまでの現金
(2)預貯金(残高合計が20万円以下である場合に限る。)
(3)保険契約解約返戻金(見込額合計が20万円以下である場合に限る。)
(4)自動車(処分見込額合計が20万円以下である場合に限る。)
ただし、初度登録から5年を経過した自動車については、なお相当な価値があることが類型的にうかがわれるもの(ハイブリッド車、電気自動車、外国製自動車、排気量2500ccを超えるものなど)を除き、価額を0円とみなすことができるものとする。
(5)居住用家屋の敷金等返還請求権
(6)電話加入権
(7)退職金債権のうち支給見込額の8分の7相当額(8分の1相当額が20万円以下である場合には、当該退職金債権の全額)
(8)家財道具
(9)差押えを禁止されている動産又は債権
前項により換価等をしないことが財産状況報告集会において裁判所によって了承された財産については、自由財産拡張の裁判があったものとして取り扱う。(引用元:福岡地裁の換価基準について│デイライト法律事務所)
銀行や消費者金融からの借入ができない
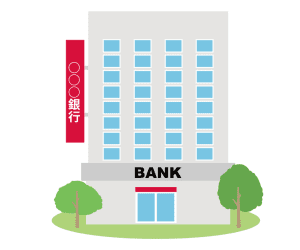
自己破産をすると、一定期間信用情報機関に債務整理の履歴が残ります。
信用情報機関にネガティブな情報が残っている間は、銀行や消費者金融でローンを申し込んでも審査通過は難しいでしょう。
信用情報機関ごとの情報登録期間は、以下のとおりです。
自己破産の記録が残る期間
中小消費者金融によっては「ブラックでも借りられる」「自己破産者でも審査通過できた」といった口コミが見られます。
しかし、実際のところは審査に柔軟な中小消費者金融であっても、自己破産者の審査通過は難しいのが実態です。
クレジットカードの新規契約や利用継続

信用情報機関にはクレジットカード会社も加盟していますので、自己破産者はクレジットカードの新規契約も難しくなります。
クレジットカードには、ショッピング機能とキャッシング機能がありますが、特にキャッシングの審査では自己破産の履歴があると審査通過は難しいでしょう。
ちなみに、自己破産をすると保有中のクレジットカードも使えなくなります。クレジットカードでリボ払いをしている場合も、分割払いの権利を失い一括返済が求められ、カードは解約となります。
ただ実際には自己破産をするときは一括で支払う能力はないでしょうし、特定の債権者だけ返済することは禁じられています。したがって、クレジットカードの残債も免責の対象となるのが一般的です。
以下は、三井住友カードの規約を一部抜粋したものです。
このなかにもあるとおり、会員が破産したときは「期限の利益の喪失」つまり、分割払いの権利を失い会員資格は消失してしまうことが記載されています。
第4章 期限の利益の喪失・会員資格の取消し・退会等
第22条(期限の利益の喪失)
1.本会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
(1)仮差押、差押、競売の申請、または破産もしくは再生手続開始の申立等の法的な債務整理手続の申立があったとき。
(引用元:三井住友カード会員規約)
弁護士や司法書士、宅地建物取引士など一部の仕事に就けなくなる

自己破産をすると、一部の職業に就くことはできなくなります。身近な例でいうと、税理士などの士業や警備員などの業務はできません。
参考までに、自己破産をすると就けなくなる職業を一部抜粋し一覧表にしています。ただ、以下を見ればわかる通り、自己破産で影響を受けるのは一部の限られた職種のみです。
一般的なサラリーマンやパート、アルバイトをしているような人は、自己破産をしてもほぼ影響はありません。
自己破産をすると就けなくなる仕事や役職
| 職種 | 具体的な職業や職務 |
|---|---|
| 士業 | 弁護士、弁理士、公認会計士、税理士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士、社会保険労務士、通関士、不動産鑑定士の登録、宅地建物取引主任者の登録、中小企業診断士の登録 |
| 一般業務 | 派遣元責任者、警備員、マンション管理業務主任者の登録、監査法人の特定社員の登録、風俗営業の営業所の管理者 |
| 金融関連 | 商品先物取引業者のための外務員の登録、金融商品取引業者等のための外務員の登録、賃金業務取扱主任者の登録、銀行の取締役、執行役または監査役、投資法人の執行役員・設立企画人・監督委員、金融商品会員制法人・自主規制法人の役員 |
| 会社の役員 | 特定非営利活動法人の役員、商工会議所の会員・役員、保険会社の取締役、執行役または監査役 |
賃貸マンションの契約(金融系の保証会社を利用する場合)
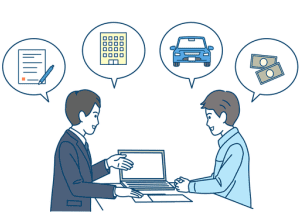
賃貸マンションを契約する際に、保証会社の契約がともなう場合は注意が必要です。なぜなら、保証会社のなかには信用情報機関に加盟している金融系の企業があるためです。
金融系の企業は、本人同意があれば信用情報機関のデータを見ることができます。
保証会社が信用情報機関に加盟していなくてもグループ会社に金融系の会社があり、個人情報を共有する旨の同意をした場合は自己破産者の審査に影響を及ぼすことがあります。
また保証会社によっては家賃の支払いをクレジットカード払いに限定している会社もありますので、事実上カードを持っていない人は審査に落ちる可能性が高くなるでしょう。
参考までに、金融系の会社が絡んでいるマンション保証会社を一覧にしていますので、参考にしてください(※ただし、必ずしもすべてのケースで、下記の会社での審査に落ちるというわけではありません)。
金融系のマンション保証会社の例
| 保証会社名 | 関係する金融機関や信販会社など |
|---|---|
| あんしん保証株式会社 | 家賃をライフマスターカードで決済するようにすすめられるため、審査通過が難しくなる可能性有 |
| 株式会社イントラスト | 大手信販会社と連携したサービスを展開しているため、本人同意のもと信用情報機関にアクセスされる可能性がある |
| 株式会社オリコフォレントインシュア | 信販会社のオリコグループのため、信用情報機関に傷があると審査落ちの可能性がある |
| ほっと保証株式会社 | ライフカードと提携しているため、カード決済で家賃支払いにした場合はマンション契約にも支障が出る場合あり |
| エポスカード(ROOM iD) | エポスカードが提供する家賃保証サービスのため、クレジットカードがないと利用できない場合がある |
| アプラス家賃サービス | 新生銀行グループが運営しているため、信用情報機関にアクセスされる可能性あり |
再度の自己破産や個人再生ができなくなる
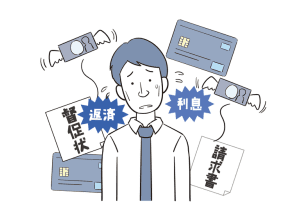
一度自己破産をして免責決定を受けると、7年間は2回目の自己破産はできなくなります。ただ、厳密にいうと自己破産ができないのではなく「免責がおりない可能性が高い」のが正解です。
自己破産の免責不許可理由のなかには、「免責許可の決定が確定してから7年以内に免責許可の申し立てがあること」と書かれています。
つまり免責を受けてから7年以内に再度免責の申し立てをしても、それは「認められない」のです。まれに、裁判所の判断で7年以内の免責決定がおりる場合がありますが、かなりハードルは高くなると思ったほうがいいでしょう。
一方、自己破産をしたあとの「個人再生」は、制度上可能です。
ただし、自己破産をしてからすぐに個人再生の申請をしても「返済能力がないのでは?」と疑われて難航するケースがほとんどです。
破産手続開始決定後の引っ越し
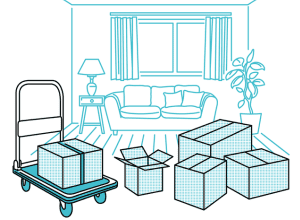
自己破産の手続きを申請してから破産手続きが開始されると、原則転居はできなくなります。
もし、やむを得ない事情があって破産手続き開始後に転居する場合は、裁判所の許可を得なければいけません。
ちなみに、破産をする場合は手持ちの不動産を手放すケースがほとんどですので、破産手続き中に転居するとなると「賃貸契約」がともないます。
前述の通り、賃貸マンションの契約をする場合、自己破産に至った人は契約できないケースも多いため、実際には転居は困難になると思ったほうがいいでしょう。
自己破産しても変わらない9つの事

自己破産をしても以下の9項目については、これまで通り変わることなく普段の生活が送れます。
- 年金の受け取り
- 携帯電話の契約(分割払いに注意)
- 選挙権
- 生命保険の継続
- 税金の支払い義務
- 生活保護の申請や受給
- 個人事業や自営業の継続
- 銀行預金や口座開設
- 旅行や出張
それぞれの項目について、詳しく解説していくことにしましょう。
自己破産しても年金はこれまで通り受け取れる
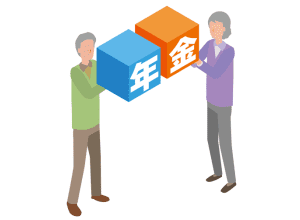
自己破産をしても、年金受給者については、これまで通り年金が受け取れます。一方、年金を支払っている人も、これまで通り年金の支払い義務は継続して残ります。
自己破産には「新得財産は処分してはならない」という法律が適用されます。新得財産とは、自己破産手続き開始後に取得した財産のことです。
自己破産したあとも年金は定期的に支給されますので、新得財産として扱われ没収されることはありません。また企業型確定拠出年金や、個人で掛け金を支払っているidecoなどの財産も守られます。
確定拠出型年金が処分されないのは「個人の将来の生活に必要なお金であるため」が主な理由です。
ただし個人年金については、自己破産をしたときに解約させられるかもしれません。個人年金は公的年金の補てんの意味合いが強い「任意の年金」です。
個人年金がなくなったとしても公的年金で老後の生活は保障されるとの考えから、裁判所によっては処分を命ぜられることもあるようです。
携帯電話の契約は継続可能(分割払いに注意)

自己破産をしているときに持っている携帯電話は、破産手続き開始後も持ち続けられます。
ただし以下のケースにおいては契約継続が困難になったり、機種代の残債を一括返済するように求められることがあります。
ケース①:自己破産に至るまでに、携帯電話料金を支払っていなかった場合
ケース②:スマホの機種代金を分割で支払っている場合
ケース①については、自己破産の有無に関わらず料金滞納者は利用停止の手続きがとられます。普段の生活で通信手段が途切れることは、生活に支障をきたします。ローンの支払いが厳しくても、携帯電話料金の支払いだけは怠らないようにしておくことが大切です。
ケース②のスマホ料金の分割支払いについてですが、スマホの分割支払いは「ローン」と同じです。機種代金の分割で滞納が発生すると、通常のローンのように延滞履歴が信用情報機関に残ります。
自己破産をしたときには、特定の業者だけ返済を継続することは許されませんのでスマホの機種代のローンについても返済がストップすることになります。
ただし、ローンで手に入れた機種を換金したとしても価値はありませんので、免責決定後もスマホは手元に残るケースが一般的です。
また、携帯料金の延滞履歴がTCA(電気通信事業者協会)にブラックリストとして残る点にも注意しましょう。
TCAには大手通信会社やケーブルテレビ会社などが加盟していますので、頻繁に滞納を繰り返しているとどこの携帯キャリアでも契約ができなくなります。
自己破産しても選挙権に影響はでない

自己破産や免責の決定を受けたとしても、選挙権はこれまで通り行使できます。
自己破産は借金を整理するための手続きであり、選挙権などの公民権を脅かすものではありません。
したがって自己破産をしたとしても選挙権は残りますし、立候補できる被選挙権も残ります。
自己破産しても生命保険は解約しなくても良い

加入している生命保険にもよりますが、破産手続き時に加入している生命保険や医療保険などは原則解約する必要はありません。
ただし、生命保険や医療保険の中には「解約返戻金」がある商品もあり、債権者に分配できる解約返戻金があると保険を解約するように命ぜられる場合があります。
具体的には、解約返戻金が20万円以上あるケースでは注意が必要です。生命保険のなかには、加入期間が長ければ長いほど解約返戻金が増え資産価値が上がるタイプの保険があります。
将来受け取れる解約返戻金を年金のかわりにしたいなどライフプランを立てている場合、解約返戻金と同じ金額を破産管財人に支払うことで、解約を免れることもあります。
ただし、いずれの場合も裁判所の決定には従う必要がありますので弁護士とよく相談して解約返戻金を守りたい理由を説明できるようにしておきましょう。
破産後も税金は従来通り支払い義務が残る

自己破産をしても変わらないもののなかには、メリットのあるものばかりではありません。
一例をあげると「税金の支払い」があります。
自己破産で免責決定を受けると、借金の返済は免除されますが税金の支払い義務は残ります。
これは、破産法253条で「非免責債権」が決められており、税金は非免責債権に該当するためです。
- 所得税
- 贈与税
- 相続税
- 市町村民税
- 固定資産税
- 自動車税
- 国民健康保険料
- 国民年金保険料
もし税金の支払いが困難な場合は、以下の対策を講じることも可能です。
1.税金の延納や分納
税金を支払いが難しい場合は、一時的に支払い期限を延納してもらうことが可能です。ただし、延納には一定の手数料が発生する点に注意が必要です。
【質問】延納を利用するには、どのようにすればよいのですか。
【回答】延納には、所得税及び復興特別所得税の延納と贈与税の延納があります。
■所得税等の延納
所得税等の確定申告については、納期限まで(振替納税の場合は振替日)に納付すべき税額の2分の1以上を納付すれば、残りの税額の納付を5月31日(5月31日が土日祝日だった場合は翌営業日)まで延長することができます。延納期間中は年0.9%の割合で利子税がかかります。
(引用元:国税庁)
2.生活保護を申請する、または低所得であることを申請し非課税にしてもらう
生活保護の認定、または一定の所得以下であることを認めてもらえれば一部の税金は減免してもらえます。
たとえば住民税については一定の条件に該当する場合、減免対象となります(※港区の公式サイトから非課税になる人の条件について一部を抜粋していますのでこちらも参考にしてください)。
【質問】住民税はどういう場合に非課税になりますか。
【回答】所得額や扶養親族の有無、または本人が未成年者、障害者、ひとり親、寡婦であるなどの条件によって課税・非課税が決定します。●非課税の制度は次の人が該当します。
(1)その年の1月1日現在で、生活保護法による生活扶助を受けている人。
(2)障害者、未成年者、ひとり親、寡婦(夫)の人で、前年の合計所得が135万円以下(給与収入なら204万4千円未満)、(令和2年度までは125万円以下)の人。
(3)前年の合計所得が一定の所得以下の人。
35万円×(本人+被扶養者の人数)+21万円(21万円は被扶養者がいる場合に加算)+10万円(令和3年度から加算)
なお、所得割の非課税の場合は、次の所得以下の人。
35万円×(本人+被扶養者の人数)+32万円(32万円は被扶養者がいる場合に加算)+10万円(令和3年度から加算)●前年の収入が以下より少ない人(合計所得が45万円以下(令和2年度まで35万円以下))
(1)アルバイトやパートの給与収入が100万円以下
(2)65歳以上で年金受給のみの人は、年金収入が155万円以下
(3)65歳未満で年金受給のみの人は、年金収入が105万円以下
(4)不動産収入等所得がある人は、収入から必要経費を引き、合計所得が45万円以下(令和2年度まで35万円以下)
(引用元:港区公式HP)
生活保護の申請

自己破産をしても、生活保護を申請したり生活保護費を受給したりすることは可能です。
なぜなら生活保護は人が最低限の生活を送るために用意された国の仕組みであり、自己破産とは関係のない制度だからです。
ちなみに、すでに生活保護を受給している人が自己破産をする場合は法テラスの民事法律扶助制度を利用すれば弁護士費用を立て替えてもらうことも可能です。
法テラスで費用の立替を依頼すると一般的には後日返済しなければいけませんが、生活保護受給者の場合は最終的に償還免除(返済の免除)される場合があります。
個人事業や自営業の継続

個人事業主や自営業を営んでいる場合、自己破産後であっても事業の継続は可能です。
ただし、実際は個人事業主が事業を継続するうえで以下のような問題が発生します。
自己破産後に個人事業主が抱える問題
1.信用情報機関に履歴が残るため事業資金が借りられない
前述の通り、自己破産の履歴は信用情報機関に残りますので事業資金を銀行から借りるといったことはできなくなります。無借金で事業を継続できるのであれば、問題ありません。
2.一部の契約関係の解消が発生する
事業を継続するためには、従業員の給与や工場や事務所の家賃を継続して支払う必要が出てきます。借金の返済がままならない…ということは、それらの支払いもできないケースがほとんどですので事実上事業が継続できないことになります。
3.取引先への支払いができなくなる
自己破産をして免責を受けると借金の支払いが免除されますが、同時に取引先への買掛金の支払いなども行えないケースがほとんどです。したがって自己破産と同時に取引先からの信用を失うため、事実上事業継続は難しくなるのが一般的です。
自己破産後の銀行預金や口座開設について

破産手続きが開始されると借入れがある銀行の口座は一時的に凍結されるため、預け入れも引き出しもできなくなります。
一方、借入れがないなど自己破産とは関係のない口座は、これまで通り利用が可能です。
ただし、借入れがないからといって自己破産で処分すべき財産を隠し持つことは許されませんのでその点は注意しましょう。
自己破産手続き後に口座が凍結されると、公共料金の引き落としもできなくなります。破産手続きを予定している場合は債務がない銀行に引き落とし口座を変更するなど、事前の手続きを忘れずに行うことが必要です。
自己破産しても旅行や出張には影響なし

自己破産をしても、旅行や出張に影響を及ぼすことはありません。
ただし、破産手続きの開始決定を受けたあとに居住地を離れて海外旅行をする場合は裁判所の許可を受けなければいけません。
下記に、自己破産を申請する前と後で、どのような点に注意すべきかまとめていますので、参考にして頂ければと思います。
| 自己破産の申請前 | 海外への旅行や出張は問題なく行ける。 ただし、弁護士に相談している段階では連絡が取れるようにしておくこと |
|---|---|
| 自己破産手続き中 | 【同時廃止事件として取り扱う場合】 居住の制限はないため、自由に海外にいくことは可能 【管財事件として取り扱う場合】 破産手続き中に、海外旅行や転居などで居住地を離れる場合は裁判所の許可が必要(破産法第37条)。 |
| 自己破産後 | 海外への移動は問題ないがクレジットカードが使えなくなるため、事実上海外での活動は制限される |
自己破産で注意すべきデメリット6つを解説

自己破産には免責を受けると借金がなくなるメリットがありますが、一方でデメリットもあります。
さきほどお伝えした「自己破産をすると変わること」の内容も含め、もう少し深堀りしてみたいと思います。
家族に自己破産がバレるリスクがある

自己破産で注意すべきなのは、「身近な人にバレる可能性がある」点です。
たとえば以下のようなケースでは、自己破産が家族にバレることがあります。
- 裁判所からの郵便物が自宅に届く
- 夫婦の共有財産がある場合や、配偶者に連帯保証人になってもらっているケース
- 保有している不動産を処分するケース
- 債権者から裁判をおこされ、給与差押えをされることでバレる
自己破産をしたときに「不動産の処分」については隠しようがありません。
一方、裁判所からの郵便物や連絡については、自宅でなく弁護士の事務所に届くようにしてくれる場合もあります。
どうしても家族にバレたくない場合は、弁護士に相談してみることをオススメします。
信用情報機関にブラックリストが残る

前述のとおり、自己破産の履歴は一定期間信用情報機関に残ります。信用情報機関の記録は、誤った登録以外は消すことはできません。
信用情報機関の情報が消えてからは収入に問題がなければローンやカードの契約は可能です。
ただし、信用情報機関に金融取引履歴がまったくないと「ホワイト状態」となり、審査に影響を及ぼす場合もあります(初回の借入限度額が少額になるなど)。
これは、信用情報機関のデータを照会した金融機関が「過去に自己破産などをした人ではないか?」と疑ってしまうためです。
新規ローンが組めなくなるほか利用中のローンは解約される

信用情報機関に自己破産の履歴が残るとローンの審査には落ちてしまいますが、破産手続き開始時に契約中のローンも解約されてしまいます。
ここで注意しないといけないのが「強硬に取り立てをしてくるローン会社への返済」です。自己破産を申請する人のなかには、いわゆる「闇金」からの借入れがある人も少なくありません。
破産手続きには債権者平等の原則というルールがあります。闇金は弁護士が介入しても強硬に取り立ててくる可能性がありますが、弁護士に委任した時点で一切返済する必要はありません。
破産手続きが正式に開始されたら、とにかく「一切のローンは返済をストップできる」と覚えておきましょう。
子どもの奨学金やローンの保証人になれない

自己破産をすると、連帯保証人になるときに影響が出ます。特に子どもがいる場合、奨学金の連帯保証人を依頼されたときは注意が必要です。
子どもが奨学金を利用する場合、親などが保証人になるケースと保証会社が保証をするケースの2つのパターンがあります。
自己破産をした人が保証人になる場合、信用情報機関に債務整理の履歴が残っている間は保証人の審査で落ちるケースがほとんどです。
もし自己破産をしたあとで奨学金の保証人になる必要が出てきたら、保証会社への保証で奨学金を利用するようにしましょう。
自己破産ができる人の条件について解説

ここで自己破産ができる人の条件についても、簡単にお伝えしておきます。自己破産をするときは、弁護士に相談するケースがほとんどでしょう。
ただ弁護士などの専門家に相談する際でも、おおまかな仕組みや条件は最低限理解しておくことが大切です。
特に「自己破産が認められる条件」は最低限理解しておかないと、弁護士への相談料が無駄になることも考えられます。
自己破産が認められる条件とは
自己破産を認めてもらうには、以下の条件を満たしている必要があります。
- 借金の返済ができない状態にあること
- 自己破産の対象としている残債が非免責債権ではないこと
- 借金を抱えた理由が免責不許可事由に該当していないこと
少々わかりづらい言葉が出てきたと思いますので、それぞれの意味について下記表にまとめていますので、参考にして頂ければと思います。
| 自己破産が認められる3つの条件 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 1.借金の返済ができない状態にあること | 自己破産を申請すると借金の返済能力が本当にないのかが確認されます。 返済能力は自己破産を申請した人や弁護士が決めることではなく、以下の要件をもとに裁判所が判断します。 <返済能力の有無を確認するポイント> ・借金の総額 ・現在の収入 ・家族構成や扶養の有無 ・生活状況申請した人が財産を持っている場合は財産処分で債権者へ返済できないかも確認されます。 |
| 2.自己破産の対象としている残債が非免責債権ではないこと | 自己破産の対象となる借金は「非免責債権以外」の借入れのみとなります。 非免責債権とは免責が認定されない債務をあらわしており、主に以下のような支払い項目が該当します。 <非免責債権の例> ・税金、社会保険料、年金 ・公共料金 ・養育費 ・罰金や慰謝料上記に該当する支払いに困っていたとしても自己破産が認められることはありません。 |
| 3.借金を抱えた理由が免責不許可事由に該当していないこと | 一例をあげるとギャンブルなどが原因で借金をして返済不能に陥っても原則免責の許可はおりません。 免責不許可事由の例としては、以下が考えられます。 <免責不許可事由の例> ・ギャンブルが原因で債務を負った場合 ・支払い能力がない。はじめから自己破産目的で借金した場合 ・財産があるのに隠ぺいし自己破産で免責許可をもらおうとしたとき |
ギャンブルや浪費が原因の借金でも自己破産は可能?
上記の表で「ギャンブルが原因の借金は免責が認められない」とお伝えしましたが、実際には認められるケースがほとんどです。
ギャンブルが原因であったとしても借金したお金でギャンブルをしたかどうかなど、細かい記録は残っていないケースがほとんどです。
また「ギャンブルが原因」ゆえに免責決定がおりなくても、返済できない状況にあるのは依然として変わりありません。
そのためギャンブルや浪費が原因で作った借金であっても、裁判官の判断で自己破産と免責が認められるケースがほとんどです。
自己破産の費用は?相談料から成功報酬までを徹底解説
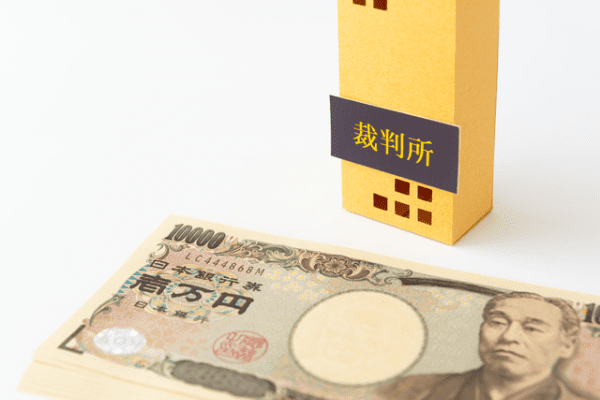
つぎに、自己破産に必要な費用についても見ていきましょう。自己破産は個人でもおこなえますが、スムーズに債務整理の手続きを進めるには法律の専門家である弁護士に依頼することをオススメします。
ただ、弁護士に依頼するとなると当然費用がかかってきます。「借金が返済できないのに弁護士費用なんて払えない」と思う人がほとんどかもしれません。
しかし、借金を放置したとしても問題は解決しません。たしかに弁護士費用はかかりますが、破産手続き中に返済はストップできますのでその間に弁護士費用を積み立てることも可能です。
弁護士相談料や着手金
弁護士に相談する時点では、30分5,500円(税込)の相談料がかかってきます。
ただ、債務整理を専門としている弁護士事務所などでは「相談料は何度でも無料」としているところもあります。
相談の結果、正式に弁護士へ依頼する場合は着手金が必要となります。
着手金とは弁護士が正式に事件解決に着手する際に必要となるお金で、弁護士によって相場が変わります。
自己破産の着手金の相場は債権者の数にもよりますが、10万円~50万円前後です。
裁判所への予納金
「予納金」は正式には引継ぎ予納金と呼ばれ、弁護士を通じて破産管財人に支払われるお金のことを指します。
自己破産手続きをする場合「同時廃止」か「管財事件」か、どちらかの方法で手続きが進められます。
| 同時廃止事件 | 処分する財産がほとんどなく、ギャンブル以外の原因で借金を作った場合 |
|---|---|
| 管財事件 | 不動産や預貯金など、債権者に分配できる財産がある場合 |
管財事件になった場合、保有している財産を査定したり調査したりすることを目的に破産管財人が任命され、引継ぎ予納金は「破産管財人への報酬」として支払われます。
予納金は原則40万円ですが、弁護士に自己破産の手続きを依頼すると半額の20万円で済みます。
ちなみに予納金を支払うタイミングは、破産申し立てから2週間~1ヶ月後です。裁判所によっては、4回の分割納付を認めているところもあります。
弁護士への成功報酬
自己破産手続きが完了した際には、弁護士への成功報酬を支払わなければいけません。
一般的に、弁護士に支払う成功報酬は「10万円~30万円」のところが多いようです。
成功報酬以外にも、弁護士が裁判所に出頭した場合には1回の出頭につき11,000円(税込)の費用がかかります。
過払い金の返還があった場合は上記以外の費用がかかることもありますので、相談時には弁護士から明確な費用を教えてもらうことが大切です。
その他実費
相談料、着手金、予納金や成功報酬のほかにも以下の費用が必要となります。
・自己破産の申し立て手数料…1,500円の収入印紙
・予納郵便切手代…東京地方裁判所本庁の場合,4,200円
・交通費や郵便切手代
・官報公告費用…10,000円~19,000円
自己破産を弁護士へ依頼するメリット
さきほど「自己破産は個人でもできるが、弁護士に依頼するのがオススメ」とお伝えしました。
ここで、再度「自己破産の手続きを弁護士に依頼するメリット」を整理しておきましょう。
- 裁判所への提出書類を作成してくれる
- 弁護士に依頼した時点で債権者からの取り立てがストップする
- 豊富な債務整理経験がある弁護士なら免責が認められるケースも多い
- 費用を分割で支払えるように配慮してくれるケースがある
上記のなかでも、やはり「債権者からの取り立てが止まる」ことは債務者にとってもっとも大きなメリットといえます。
自分で自己破産をした場合は手続きが完了するまで自分が債権者と連絡を取り合う必要があり、精神的にも負担が大きくなります。
自己破産後の人生は悲観的ではないと言える理由
自己破産にはメリットもありますが、一時的にローンが組めなかったり特定の職業に就けなくなるなど、大きなデメリットもあります。
しかし、自己破産をしても実際にはそれほど悲観する必要はありません。
一時的にローンが組めないことはそれほど苦痛ではない
自己破産をしてしまうと、最長10年間はローン契約ができません。また、契約中のクレジットカード会員資格もなくなり、新しくカードを作ることもままならない状態が続くでしょう。
しかし、実際には一時的にローンやカードが使えないことはそれほど不便ではありません。筆者も過去に個人再生の経験があり、一時的にローンやクレジットカードが使えない時期が続きました。
しかしカードがなくても貯金をして物品を購入する癖がつきましたし、どうしてもカードが必要な場合は、プリペイド式のクレジットカードもあります。
ローンを組むということは、その時点で身の丈を超えた買い物をしていることになります。手元にあるお金を使って生活していくと不思議と不安からも解消され、精神的にも楽になります。
自己破産をしても持ち家に住めるケースもある
自己破産のもう一つのデメリットは、持ち家を処分しなければいけないことです。自分ひとりならともかく家族がいる場合、転居で住所が変わってしまうことはかなりのデメリットです。
どうしても自宅を手放したくない場合は、弁護士に相談して「リースバック」の方法がとれないか協議してみることをオススメします。
リースバックとは、簡単にいうと第三者に家を購入してもらいその第三者と賃貸契約を結んで家賃を支払うことを指します。
リースバックが可能であれば、これまで住んでいた家に住み続けることも可能です。ただし、自己破産をする際は故意に財産を隠したりすることは禁じられています。
したがって、実際のところリースバックを認めてもらうには、かなりハードルが高いのも事実です。どうしても家に住み続けたい場合は、早めに弁護士へ相談するように心がけましょう。
債務整理をすることで借金体質から抜け出せるメリットも
自己破産や個人再生に限らず、債務整理をすることは「借金体質から脱却できる」メリットもあります。
自己破産をすると一時的に精神的なダメージを負いますが「二度とみじめな思いをしたくない」気持ちがわき、これまで借金に頼っていた考え方を変えられることもあります。
これまでお金が足らなくなるとついカードでキャッシングしていたかもしれませんが、債務整理をしてからは手持ちのお金で生活できるようになります。
長い目で見て「自分の考え方を変えられる」といった意味では、自己破産もメリットはあるのかもしれません。
自己破産のデメリットについてまとめ
債務整理をしたことがない人からすると自己破産はハードルも高く、自己破産後の生活がかなり制限されることを想像してしまうかもしれません。
しかし自己破産をしても「一定期間ローンが利用できない」といった制限以外は、大きなデメリットがないことはおわかり頂けたかと思います。
特に持ち家などの財産がない場合は手続きも簡単ですし、自己破産をすることで人生をやり直すことも可能です。
返済できないほどの多額借金を抱えている場合は、まずは信頼できる弁護士に相談しアドバイスを受けることからはじめてみることをオススメします。
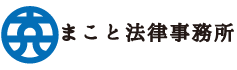
当事務所では法律のプロとして、専門知識を活かした問題解決を行っています。勝ち負けだけではなく、先を見据えた真の解決をご提案しています。
おひとりで悩まずに、まずはお気軽にお問合せください。