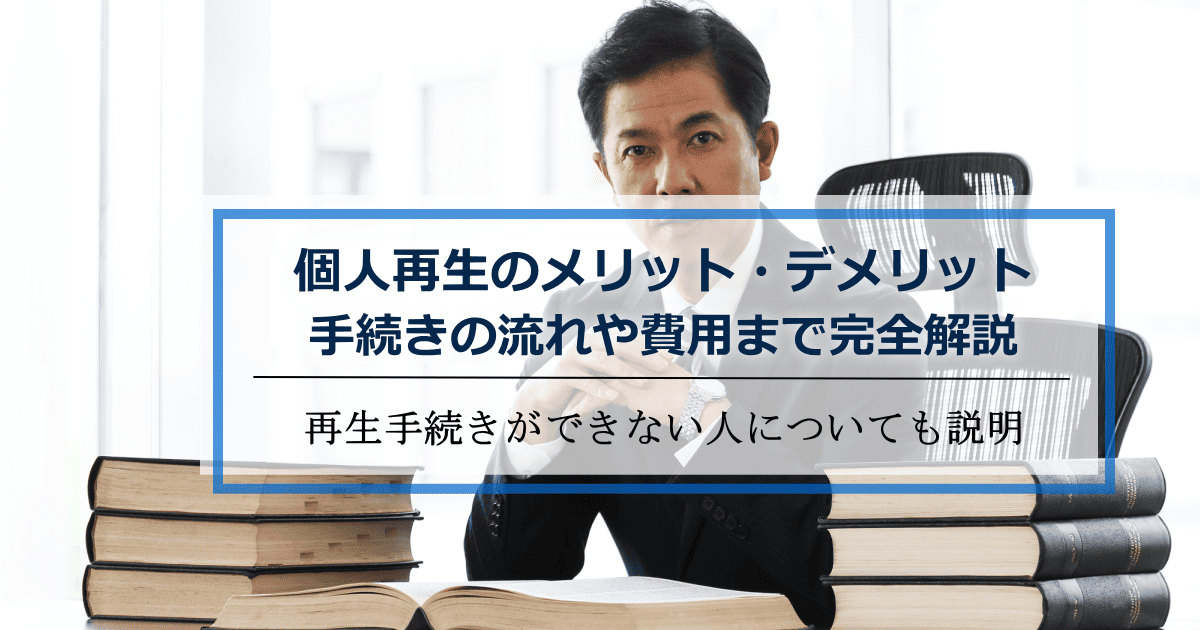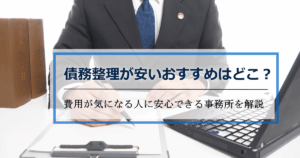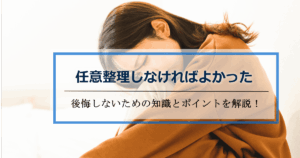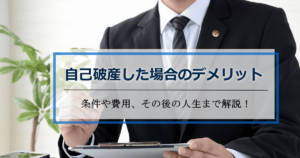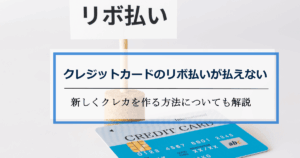個人再生は、安定した収入がある人にとって、借金を大幅に減らせる魅力的な手続きです。住宅ローン返済中の自宅がある人も、マイホームを維持したまま借金の大幅な減額ができます。
その分、手続きも複雑で時間や費用もかかるなど、誰もが気軽にできる債務整理ではありません。
また自己破産手続き同様、保証人に不利益を与える可能性もあるため、個人再生を行う際にはどのような影響があるのかを事前にしっかりと把握する必要があります。煩雑な手続きであるため、必ず専門家に相談されることをおすすめします。
個人再生を選択する5つのメリット
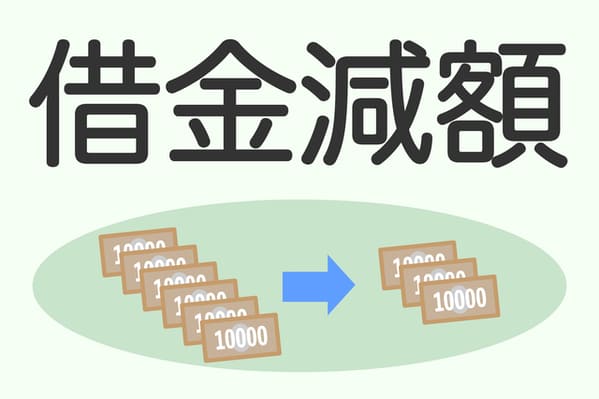
個人再生手続きのメリットは、主に次の5つです。
- 借金を5分の1程度まで減額できる(減額幅は状況によって異なる)
- 残り約2割程度の借金を(原則)3年かけて分割返済できる
- マイホームを残したまま(住宅ローンを返済しながら)借金を減額できる可能性がある
- 自動車ローンの支払いを終えていれば車を残せる
- 借金の理由は問われない
個人再生は借金を5分の1程度まで減額できる
借金の元本を大幅に減額できることが、個人再生手続きの最大のメリットです。元本を5分の1から10分の1にまで減らすことが可能です。
ただし、個人再生には借金総額によって最低限支払わなければならない金額が、次のとおり定められています。
民事再生法による最低弁済額
| 借金総額 | 最低弁済額 |
|---|---|
| 100万円未満 | 借金総額と同額 |
| 100〜500万円未満 | 100万円 |
| 500〜1,500万円未満 | 債権額の5分の1 |
| 1,500〜3,000万円未満 | 300万円 |
| 3,000〜5,000万円未満 | 債権額の10分の1 |
再生計画案が認可されるためには、法律で定められた最低弁済額以上の支払いが必要です(民事再生法231条2項3号・4号)。
また、最低弁済額は100万円と決まっているため、借金を100万円未満に減額することはできません。そのため、借金総額が100万円未満である場合は、個人再生の恩恵を受けられず手続きをする意味がないといえます。
個人再生で減額後、残りの借金を3年かけて分割返済できる
減額された後に残った借金を、数年(通常は3年、特別な事情がある場合は5年)で返済すれば残りは免除されます。毎月の返済額が大幅に減り、生活再建に余裕が生まれるでしょう。
マイホームを残したまま借金を減額できる可能性がある
個人再生手続きでは、住宅資金特別条項を利用するとマイホームを維持したまま借金の減額を実現できます。個人再生の返済を行いながら、住宅ローンについては従来通りの支払いを継続します。
ただし、住宅資金特別条項を利用するためには、次のような条件を満たす必要があります。
・住宅資金貸付債権(住宅ローンとしての借入れ)であること(民事再生法196条3号)
・再生債務者(個人再生の申立人)が所有している住宅であること(民事再生法196条1号)
・再生債務者が居住するための建物であること(民事再生法196条1号)
・住宅に住宅ローン以外の債権のための抵当権などが設定されていないこと(民事再生法198条1項ただし書)
・滞納による代位弁済後、6か月以内に再生手続き開始の申立てをしていること(民事再生法198条2項)
上記の条件を満たしているかをご自身で判断するのは難しいため、マイホームを残して個人再生を行いたい場合には、債務整理に詳しく個人再生の実績がある弁護士にご相談ください。
個人再生は自動車ローンの支払いが終わっていれば車を残せる
自動車ローンを完済している場合は、個人再生をしても車を手元に残せます。通勤や仕事で車を使用している人にとっては、大きなメリットです。
一方、自動車ローン返済中の車は、手元に残すことができません。もし、ローンを返済しながら申立を行った場合、基本的に車は引き揚げられることになります。
借金の理由は問われない
同じ債務整理手続きでも自己破産の場合は、借金の理由がギャンブルや浪費などは「免責不許可事由」とされ、支払免除が認められない場合があります。
しかし、個人再生手続きでは、借金の理由を問われることはなく、ギャンブルや浪費による借金でも手続きが可能です。
個人再生で注意したい5つのデメリット

個人再生手続きの主なデメリットは、次の5つです。
- 事故情報が登録される(ブラックリストに載る)
- 手続きが複雑で時間も費用もかかる
- ローン返済中の高価な物が処分される可能性がある
- 保証人が借金を肩代わりすることになる
- 官報に氏名と住所が掲載される
事故情報が登録される(ブラックリストに載る)
債務整理を行うと、信用情報機関に事故情報が登録されるため(いわゆるブラックリストに載ること)、クレジットカードの新規発行や新たなローンの契約が難しくなります。
信用情報機関とは、個人の返済能力や事故情報などの信用情報を管理・提供する民間の機関です。信用情報機関には主に下記の3つがあり、それぞれ加盟会社が異なります。
| 種類 | 加盟会社 |
|---|---|
| 株式会社シー・アイ・シー(CIC) | 銀行・クレジット会社・消費者金融会社・カード会社・信販会社・保証会社・保険会社・携帯電話会社など |
| 株式会社日本信用情報機構(JICC) | 消費者金融会社・カード会社・信販会社・保証会社・リース会社など |
| 全国銀行個人信用情報センター(KSC) | 銀行・信用金庫・信用組合・保証会社など |
事故情報が登録されるのは、個人再生手続きを行なった場合だけではありません。自己破産や任意整理を行なった場合も同様です。
個人の信用情報に事故情報が登録されている期間は、個人再生と任意整理では完済後5 年まで、自己破産では開始決定を受けてから7年までとされています。
個人再生は手続きが複雑で時間も費用もかかるのがデメリット
個人再生は、さまざまな書類を用意し裁判所に申立を行う法的な手続きです。
中でも、退職金や不動産、保険解約返戻金などの清算価値の計算や再生計画案の作成は、複雑な作業であり法的な知識を必要とします。そのため、手続き完了までに半年から1年ほどかかるケースもあり、その分他の債務整理に比べて費用も高額です。
個人再生を行うには、債務整理に詳しい弁護士に相談することが大切です。
ローン返済中の高価な物が処分される可能性がある
個人再生では、ローン返済中の車や高額な持ち物は処分の対象になる可能性があります。ローンを組んだりクレジットカードを利用したりして購入した商品の所有権は、支払いが完了するまで販売会社や信販会社にあります。
これを「所有権留保(しょゆうけんりゅうほ)」といいますが、ローンの支払いができなくなると、業者はその商品を引き揚げる権利があるのです。
保証人が借金を肩代わりすることになる
個人再生は、すべての借金先が手続きの対象となります。その際問題となるのは、保証人や連帯保証人がついている借金がある場合です。
個人再生手続きをすると、申立をした本人の借金は減額されますが、保証人にその効果が及ぶことはありません。そのため、保証人や連帯保証人は、全額返済の義務を負った状態になり、債権者から返済を求められることになってしまいます。
たとえば、ローンの保証人を親戚にお願いしたケースで、返済ができず個人再生をすると、保証人になってくれた親戚に迷惑がかかってしまいます。保証人がついている借金を除いて債務整理をしたい場合には、債権者を選んで手続きできる任意整理を選択する方法があります。
個人再生をしたことが官報に載る
個人再生の手続きでは、官報(国が発行している新聞のようなもの)に、手続きをした人の氏名と住所が下記の3回掲載されます。
1.個人再生の手続きが開始するとき
2.書面決議(または意見聴取)で債権者に意見を聞くとき
3.再生計画が認可決定されたとき
個人情報が度々掲載されると聞くと不安になる人もいますが、官報を読んでいる人は関連のある職業に従事しているごく一部の人に限られます。誰でも閲覧することはできますが、まず一般の人は官報について知らないことがほとんどです。
官報に自分の名前や住所が載ることを避けたい場合には、個人再生ではなく任意整理に手続きを変更する必要があります。個人再生の手続きでは、官報への掲載を避けることはできないためです。
個人再生の2つの種類と最低弁済額を解説

個人再生手続きには、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があります。どちらの手続きも、裁判所から認可決定を受けた上で、借金を大幅に減額してもらい、減額後の借金を3〜5年で返済する手続きであることに違いはありません。
ここでは、個人再生の2つの種類と違いやそれぞれの最低弁済額などについて解説します。
個人再生の最低弁済額
最低弁済額には、次の3つの基準があります。
| ①最低弁済基準 | 借金額をベースにした基準(債務額に応じて算出) |
|---|---|
| ②清算価値保障基準 | 財産を現金化した場合の価値をベースにした基準(所有している財産額に応じて算出) |
| ③可処分所得基準 | 年収から各種保険料や税金、最低生活費を引いた金額(可処分所得)の2年分以上の支払いを求める基準(収入によって算出) |
「小規模個人再生」の場合には、1か2のいずれか多い方を、「給与所得者等再生」の場合は1か2か3のいずれか多い数字を基準とします。
1.の最低弁済額基準については、上記で説明してある通りになります。
2.の清算価値保障基準については、計上される主な財産には次のようなものがあります。ただし、計上されても没収されるわけではありません。
・住宅や土地などの不動産
・預貯金
・保険解約返戻金
・退職金
・自動車
3.の可処分所得基準が用いられるのは、給与所得者等再生の手続きを行う場合に限られます。可処分所得基準は高額になりやすく、給与所得者等再生の手続きを行う人の多くはこの基準が用いられます。
小規模個人再生
小規模個人再生は、給与所得者等再生に比べて多く利用されている方法で、自営業者・フリーランス・会社員など、幅広い人が対象になります。
安定した収入があれば利用できますが(必ずしも給与所得者でなくてもOK)、債権者の半数以上の同意が得られないと不認可になってしまう可能性があります。
利用するためには、次の条件を満たしている必要があります。
・法人ではなく個人の借金であること
・借入総額(住宅ローンを除く)が5,000万円以下であること
・将来継続的に収入を得る見込みがあること
給与所得者等再生
主にサラリーマンや公務員など、将来の収入が安定している人を対象とする手続きです。
小規模個人再生より支払い総額が高くなる可能性はありますが、小規模個人再生と異なるのは、債権者の意向にかかわらず手続きを進めることが可能な点です。そのため、反対する債権者が想定されるケースでは、給与所得者等再生も選択肢に入れて検討します。
利用するためには、次の条件を満たしている必要があります。
・法人ではなく個人の借金であること
・再生債権(住宅ローンその他担保権の付いた借金を除く借金)の総額が5,000万円を超えないこと
・給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがあること
・上記収入の額の変動幅が小さいと見込まれること
規模個人再生と給与所得者等再生の主な違いを、簡単にまとめました。
| 小規模個人再生 | 給与所得者等再生 | |
|---|---|---|
| 債権者の同意 | 必要 | 不要 |
| 返済額 | 給与所得者等再生より少ない (最低弁済額と清算価値総額の大きい方の額) | 高額になる可能性が高い (最低弁済額と清算価値総額に加えて、可処分所得額2年分の最も大きい額) |
| 申立の制限 | 制限なし | 過去7年以内に自己破産や給与所得者等再生、ハードシップ免責を行っていない |
| 手続きできる人 | サラリーマン以外にも自営業・フリーランス等も可 | サラリーマン・公務員等 |
個人再生手続きの流れについて解説

まずは弁護士など債務整理を手掛けている事務所に予約を入れて、相談します。
説明に納得でき委任したいと思ったら、契約を交わして費用の説明などを受けます。必ずしもその場で依頼するかを決める必要はなく、一度自宅に戻って検討するのもよいでしょう。
依頼後は数日内(ほとんどの場合、当日か翌日)に、受任通知(介入通知)を債権者へ発送します。通知が到着して数日後には債権者からの取立てが止まります。
債権者への返済を止めると同時に、依頼した事務所へ手続き費用の分割支払い(費用の積立)を開始します。
また、住宅ローン特則を利用する場合には、銀行にも個人再生・住宅ローン特則を利用する旨の連絡を入れます。
受任通知とは?
受任通知とは、弁護士が依頼を受けて代理人に就いたことを債権者に知らせるための通知です。通知後は本人に代わって依頼を受けた弁護士が窓口となって対応します。
受任通知の送付後、債券調査票が債権者から郵送されてきます。債権調査票には、現在の借金額や取引履歴が添付されており、この情報を基に引き直し計算を行うことにより正確な債務総額が確定します。
費用の積立が順調に進めば、申立書の作成に取り掛かります。個人再生には多くの必要書類があるため、弁護士と相談して収集・作成していきます。基本的には依頼した弁護士の指示に従って進めていきましょう。
裁判所に個人再生の申立を行います。裁判所で書類が審査された後に、追加の書類や説明を求められることがあります。裁判所から求めのあった書類を追加提出することを追完といいます。弁護士から追完書類について連絡があれば、迅速に対応しましょう。
書類の審査に通ると、裁判所から再生手続開始決定が出ます。このとき、裁判所により個人再生委員が選任される場合がありますが、選任されるかどうかは地方裁判所の運用や状況によって異なります。
また、裁判所から今後の返済ができるかどうかを判断するために、「再生計画による弁済見込額の積立て」を指示されます。この手続きは、「履行テスト」と呼ばれ、3〜6か月の期間に積立を行うことが一般的です。
個人再生委員とは?
個人再生委員とは、個人再生の手続きをする上で裁判所により手続きの指導・監督をする人であり、申立裁判所の管轄内にある事務所の弁護士が選任されることが一般的です。
開始決定後、まず債権者に債権額の確認をします。債権者から異論があれば意見が出され、こちらからも反論できます。双方の主張を出し合い、債権額を確定させます。
債権者から提出された債権届出書に記載された債権額について確認・判断し、債権認否一覧表を裁判所に提出します。
確定した債務額をもとに、再生計画案を作成・提出します。
再生計画案は、個人再生手続きの鍵を握る重要なポイントです。無理のない返済で生活の立て直しを図れるかどうかが、重要になります。
再生計画案に記載する主な内容は、次の通りです。
・返済の開始時期(いつから返すのか)
・返済総額(どの程度減額されていくら返すのか)
・返済方法(どのように返すのか)
・返済期間(どのくらいかけて返すのか)
・住宅ローン特則(住宅資金特別条項)の利用の有無
裁判所に提出された再生計画案が、実現可能かどうか、債権者が納得できる内容かを確認する手続きです。
小規模個人再生手続きの場合は、裁判所から各債権者に再生計画案と議決書が郵送される「書面による決議」が行われます。不同意の債権者は期限までに書類を提出しますが、特に意見がなければ(反対でなければ)回答をしないことになります。
給与所得者等再生手続きの場合は「意見聴取」が行われますが、意見を聞くだけで同意は不要です。
再生計画案が裁判所や債権者から認められると、裁判所より再生計画認可決定が出されます。
小規模個人再生の場合、債権者数の2分の1以上の反対がなく、かつ反対した債権者の債権額の合計が全債権額の2分の1を超えていないことが条件になります。
裁判所による再生計画の認可から1か月ほどで、認可された再生計画が確定します。認可決定の確定を受けたところで、申立続きに関する一通りの業務は終了となります。
依頼した専門家から返済スケジュルーや返済先の情報(振込先)などの書類を受け取り、返済開始に備えます。履行テストで積み立てたお金は返還されます。
再生計画認可決定が確定した月の翌月より、再生計画で定めた返済計画に沿って返済を開始します。返済は原則3年で、各債権者の指定する口座に毎月遅れないよう入金します。
返済を続ける中で、もし支払いを継続できそうにない状況になったら、手続きを依頼した専門家に再度相談しましょう。黙って返済を滞納すると再生計画認可決定が取り消される可能性があり、そうなると減額もなかったことになってしまいます。
専門家に相談することで、支払い期間の延長や、場合によっては方針変更など取れる対策を一緒に考えてくれるでしょう。
個人再生手続きにかかる期間

個人再生は他の債務整理に比べ、確認事項やそろえる資料の多さ、手続きの複雑さから時間と手間がかかるとされている手続きです。手続きにかかる期間は、1年~1年半程度と長期になります。地方裁判所によって運用方法が異なるため、詳しい期間を知りたい場合は確認が必要です。
| 手続き | 期間 |
|---|---|
| 依頼~申立 | 半年~1年 |
| 申立~再生手続き開始決定 | 1~2か月 |
| 再生手続き開始決定〜再生計画案提出 | 3~4か月 |
| 再生計画案提出〜再生計画認可決定 | 1~3か月 |
専門家への依頼から裁判所へ申立てするまで、通常で半年~長いと1年程度の準備期間が必要になります。弁護士費用(着手金)をこの期間に分割払いすることもあります。
裁判所への申立てから再生手続開始決定が出るまで、特に問題がなければ通常1か月ほどです。
再生手続開始決定が出てから再生計画案の提出までは、通常3〜4か月程度かかります。個人再生委員が選任されて履行テストが行われた場合、さらに最大6か月程度の期間がプラスされる可能性があります。
再生計画案を提出してから裁判所より認可決定が出るまで、1〜3か月かかります。
【手続きにかかる期間を短くするポイント】
裁判所に申立てを行うまでの準備をすみやかに行うことができれば、その分手続完了時期を早められるでしょう。そのためには、弁護士から求められた書類の収集など迅速に対応するようにしましょう。
個人再生手続きの費用

個人再生手続きにかかる費用の相場は、50万~80万円程度です。
内訳として、裁判所に支払う費用(約1〜20万円)と弁護士費用(約50〜60万円)があり、それらを合わせて約50〜80万円が目安となります。
裁判所に支払う費用
裁判所に支払う費用の内訳は、次表のとおりです。
| 内訳 | 内容 | 費用相場 |
|---|---|---|
| 申立手数料(収入印紙代) | 裁判所に提出する申立書に貼る収入印紙 | 1万円程度 |
| 予納郵券代 | 裁判所から債権者へ個人再生手続に関する通知などを送るための郵便切手代 | 2,000円程度 ※管轄裁判所や債権者数により異なる |
| 官報公告費 | 官報に掲載する際にかかる費用 | 1万3,744円 |
| 個人再生委員の報酬 | 個人再生委員を選任する場合に裁判所に納める費用 | 15万円~25万円程度 ※個人再生委員が選任される場合のみ |
弁護士に支払う費用
弁護士に支払う費用の内訳は、次表のとおりです。
| 内訳 | 弁護士の費用相場 |
|---|---|
| 相談料 | 無料~1万円程度 |
| 着手金 | 20万円~50万円程度 |
| 報酬金 | 30万円~40万円程度 |
| その他実費など | 3万円~5万円程度 |
| 合計金額 | 50万円~80万円程度 |
弁護士費用は、法律事務所により設定や金額が異なることがあります。たとえば、着手金はなしとする代わりに事件終了時の報酬金を高額に設定する事務所や、着手金・報酬金と分けて請求せず、一括で請求する事務所もあります。
そのため、複数の法律事務所の費用を比較する際場合には、費用の合計額がいくらになるかで判断する方がよいでしょう。
個人再生の費用が一括で支払えない場合は、分割払いや後払いに応じてくれる事務所もあります。債務整理の取り扱い実績が豊富な事務所に、借金相談してみましょう。
【個人再生の費用を支払うのが難しい場合】
個人再生の手続き費用は高額です。資力や収入が一定額以下の人は、法テラスの民事法律扶助制度を利用できる可能性があります。 利用できる条件など詳しく知りたい場合は、問い合わせてみることをおすすめします。
参考:法テラス(日本司法支援センター)「無料法律相談・弁護士等費用の立替」
個人再生手続きができない人とは

個人再生手続きができないのは、次のようなケースです。1つずつ順を追って確認しましょう。
・個人再生の3つの条件を満たしていない(個人の借金ではない・安定した収入がない・負債総額が5000万円以上である)
・多額の財産を所有している
・特定の債権者に対する借金のみ個人再生しようとしている・偏頗弁済をしている
・債権者から不同意があった
・手続き費用を用意できない
・再生手続き開始の申立の棄却・却下事由に該当する
・借金総額が100万円未満である
個人再生の3つの条件を満たしていない
個人再生を申立する条件としてすでに次の3つがあることを述べました。
・個人の借金であること
・負債総額(住宅ローンを除く)が5,000万円以下であること
・将来継続的に収入を得る見込みがあること
これらに該当しない場合は申請をしても認められないため、個人再生手続きはできません。
多額の財産を所有している場合
個人再生は財産を維持したまま行える手続きですが、多額の財産を所有している場合には弁済額が高額になってしまいます。
多額の財産を所有している場合、「清算価値」が高額になります。清算価値が「最低弁済額」を上回る場合、高額な清算価値が最低弁済額に適用されます。これは、「清算価値保障原則」と呼ばれ、個人再生での減額において、財産を処分した場合の金額以上を返済する義務があるという定めによります。
したがって、多額の財産を所有している人には、個人再生は向いていない手続きといえるでしょう。
【偏頗弁済をしている】特定の債権者の借金のみ個人再生している
個人再生手続きは、平等にすべての借金を対象としなければなりません。親戚や友人の借金だけを先に全額返済して、消費者金融の借金だけを個人再生手続きで減額してもらうということはできません。
申立前に一部の債権者にだけ返済していることが、後で判明したような場合も同様です。
偏頗弁済(へんぱべんさい)と判断されると、本来は存在したはずの資産として扱われ返済額が増えたり、再生計画案が認可されなかったりする可能性があります。
債権者から不同意(反対)があった
債権者が個人再生に反対すると、個人再生手続きを行えないことがあります。
あらかじめ反対されることがわかっている場合には、債権者の同意が不要な給与所得者等再生手続きについて、弁護士と相談してみましょう。
個人再生手続き費用を工面できない
個人再生の手続きを行うと先程お伝えした裁判所や法律事務所などに支払う費用が発生します。費用を用意できない場合、個人再生の手続きを行うことができません。
そのような場合には、分割払いに対応している事務所を探したり、法テラスに相談可能か問い合わせてみたりするなどの対策を考えましょう。
再生手続き開始の申立の棄却・却下事由に該当する
民事再生法で定められている、再生手続き開始の申立の棄却理由に該当する場合、個人再生ができないことがあります。
民事再生法25条(再生手続き開始の条件)
次の各号のいずれかに該当する場合には、裁判所は、再生手続開始の申立てを棄却しなければならない。
一 再生手続の費用の予納がないとき。
二 裁判所に破産手続又は特別清算手続が係属し、その手続によることが債権者の一般の利益に適合するとき。
三 再生計画案の作成若しくは可決の見込み又は再生計画の認可の見込みがないことが明らかであるとき。
四 不当な目的で再生手続開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき。
(引用元:e-Gov 法令検索)
上記の二と三について、わかりやすく解説します。
二は、すでに自己破産の手続きをしていて、個人再生をするよりも自己破産をしたほうが債権者にとって利益があると考えられる場合です。
三は、再生計画を組んでみたが、「毎月の返済額が高額で返済が継続できそうにない」、「申立人の収支状況から考えて支払い計画が現実的ではない」と明らかに判断される場合です。
借金総額が100万円未満の場合は個人再生をする必要がない
上記で説明した最低弁済額表のとおり、借金総額が100万円未満の場合は個人再生をしても借金が減らず、手続きをする意味がありません。
そのため借金が100万円未満の場合は、利息カットや返済期間の見直しを債権者に交渉する任意整理を選択しましょう。
個人再生で失敗しないためには│まとめ
個人再生を正しく活用できれば、借金を大幅に減らし、人生再スタートの大きなチャンスとすることができます。
しかし、申立てをすれば必ず成功するとは限りません。
個人再生を失敗しないためには、正確な情報を速やかに提出することや、安定した収入、無理のない返済計画などが不可欠です。
中でも重要なポイントは、早い段階で債務整理に強い弁護士に相談することです。同じ状況でも、相談・依頼の時期が早いとその分入念な準備や対策に時間を割くことができるため、手続きの正確性や成功率が上がります。
借金に悩んでいる方は、まず信頼できる専門家を見つけて相談し、早目のタイミングで再出発に向けた一歩を踏み出しましょう。
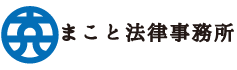
当事務所では法律のプロとして、専門知識を活かした問題解決を行っています。勝ち負けだけではなく、先を見据えた真の解決をご提案しています。
おひとりで悩まずに、まずはお気軽にお問合せください。