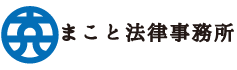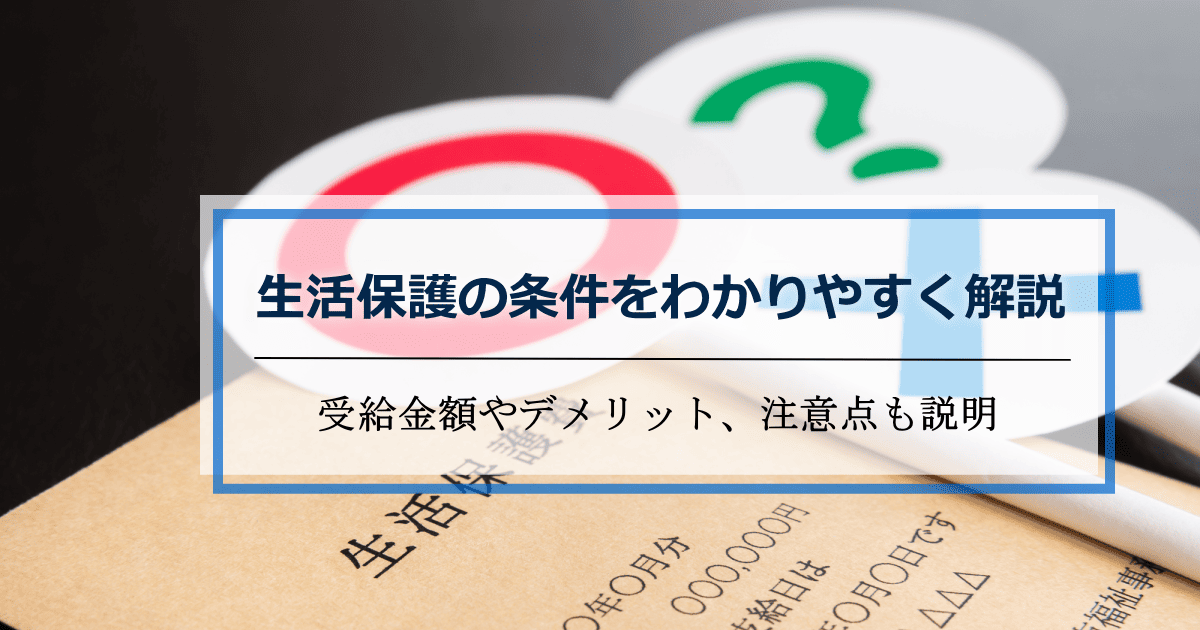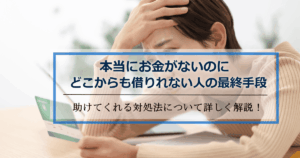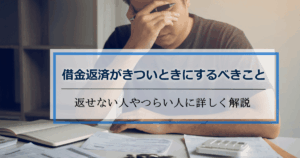本記事は、生活保護に関する解説記事です。
以下のような疑問や悩みを持っている方向けに、生活保護についてわかりやすく解説しています。
- 経済的に生活が苦しく、生活保護を受けたい
- 生活保護を受けるための条件を知りたい
- 生活保護を受けるにあたってどのようなデメリットが発生するのか知りたい
生活保護とは、経済的に生活が困難である世帯を対象に必要最低限の生活費を保障してくれる公的な制度のことです。困窮している程度に合わせた生活保護を国がおこない、健康で文化的な最低限度の生活が保障されます。
また、本人の自立を助長する制度でもあるので、就労の意思がある場合それに向けた助言や指導を受けることも可能です。ほかにも生活保護の受給金額や受給金額の加算要件など、金額に関することもわかりやすく解説しています。
自分の住んでいる地域や現在の生活状況などでも受給可能な金額は異なるので、いくらまで保障されるか具体的に知りたい方はぜひ参考にしてください。
生活保護の申請から受給までの流れを解説

はじめに、生活保護の申請から受給までの流れについて解説していきます。
手順通り、下記表でまとめていますので参考にしてください。
生活保護の利用を希望する場合、まず最寄りの福祉事務所の生活保護担当へ相談します。生活保護の詳細について説明を受けるとともに、生活福祉資金や各種社会保障など、他の公的制度を活用できないかについて検討します。
生活保護の受給を申請するにあたって下記のような調査を受けます。
- 生活状況などを把握するための調査(家庭訪問など)
- 預貯金や保険、不動産などの資産に関する調査
- 扶養義務者に関する調査(仕送りなどの援助が可能かどうか)
- 年金や社会保障給付、収入に関する調査
- 就労の可能性についての調査
保護費の支給については以下のとおりです。
- 厚生労働大臣が定める基準をもとにした最低生活費から、収入などを差し引いた金額を保護費として毎月支給される
- 生活保護を受給している期間は、毎月収入の状況を申告する
- 世帯の実態に応じ、福祉事務所のケースワーカーが年に数回、訪問調査をおこなう
- 就労の可能性がある場合、就労に向けた助言や指導を受ける
生活保護を受けるための条件とは

生活保護は、誰でも受給できるわけではありません。ただし、下記4つの条件を満たす方であれば受給しやすいといえます。
- 申し込み者の世帯年収が住んでいる地域の最低生活費を下回っていること
- 生活に必要ないと判断された資産がないこと
- 身内からの援助が受けられないこと
- 病気や障害で働けないこと
ここからは、生活保護を受給できる4つのおもな条件について詳しく解説していきます。
受給するにあたって申請者の収入(公的給付や扶養者の援助も含む)や保有している資産、身体的な状況は重要な要件です。
受給できる金額もそれぞれの条件によって異なるので、気になるかたは下記の解説をよく確認しておくことをおすすめします。
申込み者の世帯年収が住んでいる地域の「最低生活費」を下回っていること
生活保護を受給できる人の収入条件は「申し込み者の世帯年収が住んでいる地域の最低生活費を下回っていること」です。
厚生労働省の公式サイトでは、支給される保護費について以下のように記載しています。
支給される保護費について
厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費と収入を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。
(引用元:厚生労働省 生活保護制度より)
ここで記載されている「収入」とは、単に労働によって得た収入だけではありません。
収入として計算されるものには、おもに以下のものも含まれるので確認しておきましょう。
- 車や不動産の売却金
- 年金
- 退職金
- 失業保険などの公的手当
- 生命保険などの各種保険金
- 親族からの仕送り金
独身世帯の場合はその方のみの収入を基準にしますが、世帯内に複数いる場合はその世帯全員分の収入を基準にして生活保護を受給できるかが決まります。
まとめると、自分と家族全員の収入を足しても住んでいる地域の最低生活費を下回る場合に限り、生活保護は受給可能となります。
地域ごとの最低生活費についてはのちに詳しく解説します。
生活に必要ないと判断された資産がないこと

申し込み者の持っている資産によっては、福祉事務所のケースワーカーに売却を求められることがあります。
生活保護を受給するためには、生活に必要ないと判断された資産は売却して生活費をおぎなうことが一般的です。
厚生労働省は、生活保護を受給するための資産条件について以下のように回答しています。
Q.生活保護の受給中、守らなければならないことはありますか?
A.生活保護を受給する方は、以下のような義務と権利があります。
• 利用し得る資産、能力その他あらゆるものを生活のために活用しなければなりません。
• 能力に応じて勤労に励み、健康の保持及び増進に努め、収入、支出その他生計の状況を適切 に把握するとともに、支出の節約を図り、その他生活の維持・向上に努めなければなりません。
• 福祉事務所から、生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導又は指示を受けた ときは、これに従わなければなりません。
(引用元:厚生労働省 生活保護に関するQ&A)
生活保護受給にあたって、生活に必要ないと判断されやすいおもな資産は以下のとおりです。
- 高級車
- 貴金属やブランド品
- 株や貯蓄性のある保険商品(終身・養老保険など)
- 使用していない土地などの不動産
- 必要以上のケータイやパソコン(2台所持など)
上記で記載してあるものについて必ず売却を求められるとは限りません。
たとえば車がないと生活が著しく不便になる場合は、車の所持を認められることもあります。
下記は自動車保有に関する厚生労働省の回答です。
Q.自動車を持っていても、生活保護は受給できますか?
A. 自動車は資産となりますので、原則として処分していただき、生活の維持のために活用して いただくことになります。ただし、障害をお持ちの方の通勤、通院等に必要な場合等には自動 車の保有を認められることがあります。お住まいの福祉事務所にご相談ください。
(引用元:厚生労働省 生活保護に関するQ&A)
そのほかにも、ローンを払い終えている住宅や10万円程度までの預貯金、生活家電や生活に必要な携帯やパソコンなどは所持を認められることが一般的です。
資産については担当のケースワーカーとよく相談しておきましょう。
生活保護の条件は身内からの援助が受けられないこと

一般的に生活保護を受給することよりも、親族や身内から援助を受けることを優先されます。親族や身内から援助を受け、最低限以上の生活が可能な場合は生活保護の受給対象となりません。
ただし、3親等以内の親族に扶養の意思がない場合は生活保護の受給対象となります。
親族や身内の援助については、以下の成人しているかたに「扶養調査書」が送られ、扶養の意思が調査されます。
- 両親
- 兄弟姉妹
- 別居している配偶者
- 子ども、甥姪、孫
- 祖父母、叔父叔母
期日までに扶養調査書の返信がない、扶養の意思がないと判断された場合、生活保護の受給が可能です。
親族や身内から援助があっても、全体収入が住んでいる地域の最低生活費を下回る場合はそちらも受給対象となります。
なお、生活保護申請でよくある誤解について厚生労働省は以下のように記載しています。
生活保護でよくある誤解例
扶養義務者の扶養は保護に優先しますが、たとえば、同居していない親族に相談してからでないと申請できない、ということはありません。
(引用元:厚生労働省 生活保護を申請したい方へ)
たとえば家庭内暴力などにより生活を別にした場合は、現住所を知られたくないケースがほとんどだと思います。
そんなときは、担当者に事前に相談しておけば連絡されることはありません。配偶者や親などからの家庭内暴力があった場合は必ず担当者に相談しておきましょう。
なお、この場合は扶養調査もおこなわれることはないので安心して申し込めます。
病気や障害で働けないこと
病気や障害などの理由で働けない場合、低収入になりやすいといえます。もちろんこの場合も、収入が住む地域の最低生活費を下回れば生活保護の受給対象です。
ただし、年金や公的な手当が利用できる場合はそちらの利用が優先されるので注意しましょう。
以下は厚生労働省が生活保護の受給要件について記載している内容です。
年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用してください。
(引用元:厚生労働省 生活保護を受けるための要件及び生活保護の内容)
生活保護以外の制度や公的な手当を受給できない場合は、生活保護を申し込みましょう。病気や障害が理由で働けない場合は、働けない理由について証明する必要があります。
福祉事務所へ相談に行くときは「障害者手帳」や「診断書」を持っていくと手続きを楽に進めやすくなります。
特に、病気が原因の方は確実に病状を伝えるためにも診断書を利用することがおすすめです。
生活保護の申し込みを検討する時点で、担当の医師に相談しておきましょう。
生活保護でもらえる金額を地域や扶養人数別に解説
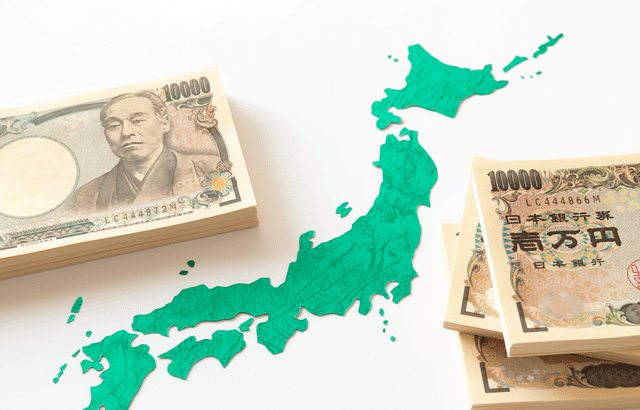
生活保護でもらえる金額は全員が同じわけではありません。
ここからは、生活保護で実際にいくらもらえるのか、その金額について詳しく解説していきます。
住んでいる地域や家族状況、障害者かどうかなど受給できる金額は人それぞれです。
自分の状況を把握し、生活保護が受給できるようになったらいくらもらえるようになるのか、ぜひ参考にしてみてください。
地域によって級地区分(生活保護の基準額)は異なる
住んでいる地域ごとに生活保護の受給額が異なる理由は、地域ごとの家賃や物価が異なるためです。
たとえば、同じ間取りの部屋でも都心と田舎では家賃に差が生まれます。食品などの値段も都心部のほうが高くなる傾向があります。
これらの差を縮めるために、住んでいる地域で受給額が異なるのです。具体的に、主要地域を例にして表にまとめていますので参考にしてみてください。
また、寒冷地に住む方は「冬季加算」の対象となる可能性があるので確認しておきましょう。
詳しくは厚生労働省の「級地区分」から確認できます。
地域による地域区分(主要地域)
| 地域区分 | 主要地域 |
|---|---|
| 1級地−1 | 東京23区、八王子市、さいたま市、横浜市、大阪市、京都市、名古屋市 など |
| 1級地−2 | 札幌市、所沢市、千葉市、青梅市、相模原市、大津市、広島市、福岡市 など |
| 2級地−1 | 小樽市、青森市、盛岡市、三郷市、柏市、羽村市 海老名市、静岡市、長野市、豊橋市、奈良市、下関市、鹿児島市、那覇市 など |
| 2級地−2 | 登別市、多賀城市、土浦市、足利市、上田市、大垣市 安城市、桑名市、加古川市、防府市、飯塚市、佐世保市、荒尾市 など |
| 3級地−1 | 北見市、八戸市、大船渡市、石巻市、米沢市、いわき市、つくば市、栃木市、渋川市 幸手市、成田市、燕市、能美市、山梨市、佐久市、彦根市、舞鶴市、米子市、鹿屋市、石垣市 など |
| 3級地−2 | 1級地−1、1級地−2、2級地−1、2級地−2、3級地−1のいずれにも該当しない地域 |
上記のように生活保護の基準額は各地域で区分されていて、それぞれ受給できる金額が異なります。
地域区分や冬季加算などについて、厚生労働省は現在見直しを検討している段階なので今後の制度変更の動きには注意するべきといえます。
主要都市別の生活保護基準額
主要都市(東京・大阪・福岡)を例に、実際に受給できる毎月の金額も表にして紹介します。
すべて20歳〜40歳の1人暮らし世帯で紹介しているので、必ず紹介した金額と同額が受給できるわけではないので注意してください。
母子加算や障害者加算、児童養育加算などについては下記で詳しく解説しています。
東京都(千代田区)の生活保護基準額(1人暮らし20歳〜40歳)
東京都千代田区で1人暮らしをしている世帯の方は、毎月最大「130,010円」の生活保護金を受給できます。
労働や、その他による収入がある場合、130,030円から収入額を差し引いた金額の受給となるので注意してください。
また、加算対象の方は紹介した金額以上の生活保護金を受給可能です。
| 項目 | 生活保護基準額 |
|---|---|
| 生活扶助 | 76,310円 |
| 住宅扶助 | 53,700円 |
| 合計 | 130,010円 |
大阪府(大阪市)の生活保護基準額(1人暮らし20歳〜40歳)
大阪府大阪市で1人暮らしをしている世帯の方は、毎月最大「116,310円」の生活保護金を受給できます。
労働や、その他による収入がある場合、116,310円から収入額を差し引いた金額の受給となるので注意してください。
| 項目 | 生活保護基準額 |
|---|---|
| 生活扶助 | 76,310円 |
| 住宅扶助 | 40,000円 |
| 合計 | 116,310円 |
福岡県(福岡市)の生活保護基準額(1人暮らし20歳〜40歳)
福岡県福岡市で1人暮らしをしている世帯の方は、毎月最大「109,720円」の生活保護金を受給できます。
労働や、その他による収入がある場合、109,720円から収入額を差し引いた金額の受給となるので注意してください。
| 項目 | 生活保護基準額 |
|---|---|
| 生活扶助 | 73,720円 |
| 住宅扶助 | 36,000円 |
| 合計 | 109,720円 |
一人暮らしや家族がいる場合の支給額
生活保護で受給できる金額は世帯の人数によって異なります。
1人で暮らすよりも、家族数人で暮らす方が生活費は高くなりやすいので、人数が多いほど受給できる金額は高くなります。
ただし、世帯の誰かに収入がある場合、受給額から収入額を差し引いた金額が支給されるので注意しましょう。
以下で1人暮らしの場合と、扶養家族がいる場合の受給額の違いついてわかりやすく解説していきます。
下記の表は、1級地−1の地域で受給する生活保護費の比較表です。
一人暮らしの場合
1人暮らし(20歳〜40歳)世帯の生活保護費
| 地域 | 生活扶助 | 住宅扶助 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 東京23区 | 76,310円 | 53,700円 | 130,010円 |
| 埼玉県川口市 | 76,310円 | 47,700円 | 124,010円 |
| 神奈川県横浜市 | 76,310円 | 52,000円 | 128,310円 |
| 大阪府大阪市 | 76,310円 | 40,000円 | 116,310円 |
地域によって差はありますが、1級地−1の地域であれば1人暮らし世帯でも11万円〜13万円程度の生活保護費の受給が可能です。
「住宅扶助」の注意点は、共益費や光熱費、水道代などが対象外となることです。
たとえば東京23区に住む場合、家賃が50,000円の物件に住むときに毎月支給される住宅扶助は、上限額が適用されず50,000円になります。
ただし、敷金や礼金など一時的に住宅扶助として認められるものもあります。詳しくは福祉事務所にて相談してみましょう。
扶養家族がいる場合
扶養家族(20歳〜40歳が2人、小学生が1人)がいる世帯の生活保護費
| 地域 | 生活扶助 | 住宅扶助 | 児童養育加算 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 東京23区 | 149,796円 | 69,800円 | 10,190円 | 229,786円 |
| 埼玉県川口市 | 149,796円 | 62,000円 | 10,190円 | 221,986円 |
| 神奈川県横浜市 | 149,796円 | 68,000円 | 10,190円 | 227,986円 |
| 大阪府大阪市 | 149,796円 | 52,000円 | 10,190円 | 211,986円 |
上記の表は20歳〜40歳が2人と、小学生が1人いる世帯で受給できる生活保護基準額を算出したものです。
1級地−1の地域に住んでいる場合、21万円〜23万円程度の生活保護費の受給が可能です。
1人暮らしの世帯と比較して生活扶助も住宅扶助も大幅に上限額が上がります。子どもがいる場合、児童養育加算がされます。
各加算項目については下記の「加算項目に該当すれば支給額も違ってくる」を参考にしてください。
「住宅扶助」の注意点は、共益費や光熱費、水道代などが対象外となることです。
たとえば東京23区に住む場合、家賃が60,000円の物件に住むときに毎月支給される住宅扶助は、上限額が適用されず60,000円です。
ただし、敷金や礼金など一時的に住宅扶助として認められるものもあります。また、世帯の誰かに収入がある場合、基準額からその収入を差し引いた金額を受給することになります。詳しくは福祉事務所にて相談してみましょう。
加算項目に該当すれば支給額も違ってくる
下記の加算項目に該当するものがある場合、生活扶助の基準額から毎月加算されます。
- 妊産婦加算
- 障害者加算
- 介護施設入所者加算
- 在宅患者加算
- 放射線障害者加算
- 児童養育加算
- 介護保険料加算
- 母子加算
これらの加算項目に該当する条件や、加算額の例について詳しく解説していきますので気になるかたは参考にしてください。
なお、加算額は1級地−1の地域で令和3年4月時点での基準額となります。詳しい加算額は福祉事務所にて相談しましょう。
妊産婦加算
妊娠中および産後から6ヶ月以内の生活保護受給者に対し、妊産婦加算が生活扶助に加算されます。
目的は、栄養補給などの経費を補てんするものとされています。加算額は下記のとおりです。
妊産婦加算の金額(1級地−1の場合)
| 妊娠6ヶ月未満の場合 | 9,130円 |
|---|---|
| 妊娠6ヶ月以上の場合 | 13,790円 |
| 産後の場合 | 8,480円 |
【加算の概要】
妊産婦(妊娠中及び産後6ヵ月以内)である被保護者に対し、追加的に必要となる栄養補給等の経費を補填するものとして支給
(引用元:厚生労働省 【参考資料】生活保護制度の概要等について)
障害者加算
障害者である生活保護受給者に対し、居住環境の改善をおもな目的とした費用が加算されます。
なお、身体障害者障害等級ごとに加算される金額が異なります。下記表を参考にしてください。
障害等級ごとの加算額(1級地−1の場合)
| 1・2級の場合 | 26,810円 |
|---|---|
| 3級の場合 | 23,060円 |
【加算の概要】
障害者である被保護者に対し、追加的に必要となる居住環境の改善のための費用や点字新聞などの雑費等の経費を補填するものとして支給
(引用元:厚生労働省 【参考資料】生活保護制度の概要等について)
障害等級について詳しく知りたい方は厚生労働省の障害等級表を参考にしてください。
介護施設入所者加算
介護施設に入所している生活保護受給者に対し、嗜好品や娯楽費として使用できる金額が加算されます。加算額は「9,880円」です。
【加算の概要】
介護施設に入所している被保護者に対し、理美容品等の裁量的経費を補填するものとして支給(例.タバコ等嗜好品、教養娯楽費等)
(引用元:厚生労働省 【参考資料】生活保護制度の概要等について)
在宅患者加算
結核、または3ヶ月以上の治療期間を要する患者が在宅で療養する場合に、患者である生活保護受給者に対し生活扶助に加算されます。
目的は、栄養補給などのために使用する経費を補てんするものとされています。加算額は「13,270円」です。
【加算の概要】
在宅で療養に専念している患者(結核又は3ヶ月以上の治療を要するもの)である被保護者に対し、追加的に必要となる栄養補給等のための経費を補填するものとして支給
(引用元:厚生労働省 【参考資料】生活保護制度の概要等について)
放射線障害者加算
放射能によって負傷、病気にかかった場合に患者である生活保護受給者に対して、生活扶助に加算されます。
目的は、栄養補給などのために使用する経費を補てんするものとされています。また、現患者と元患者で加算額が異なるので下記表を参考にしてください。
放射線障害加算額について
| 現罹患者 | 43,830円 |
|---|---|
| 元罹患者 | 21,920円 |
【加算の概要】
放射能による負傷、疾病の患者である被保護者に対し、追加的に必要となる栄養補給等のための経費を補填するものとして支給
児童養育加算
児童(18歳までの子ども)の養育者である生活保護受給者に対し、生活扶助に加算されます。
目的は、子どもの健全育成費用を補てんするためのものとされています。加算額は児童1人につき「10,190円」です。
【加算の概要】
児童の養育者である被保護者に対し、子どもの健全育成費用(学校外活動費用)を補填するものとして支給
(引用元:厚生労働省 【参考資料】生活保護制度の概要等について)
介護保険料加算
介護保険の第1号被保険者である生活保護受給者に対し、生活扶助に加算されます。
目的は、介護保険料を納付するための費用を補てんするためのものです。加算額は「実費」なので人それぞれ金額が異なります。
【加算の概要】
介護保険の第1号被保険者である被保護者に対し、納付すべき介護保険料に相当する経費を補填するものとして支給
(引用元:厚生労働省 【参考資料】生活保護制度の概要等について)
母子加算
1人親世帯の生活保護受給者である親に対し、生活扶助に加算されます。目的は、2人親世帯と同等の生活水準を保つための費用を補てんするためです。
母子加算という名称ですが、母子世帯・父子世帯に対しても支給されます。加算額は、子どもが1人の場合「18,800円」です。
一定の要件を満たすことで、経過的に加算されます。より詳しく知りたい場合は、福祉事務所に相談しておくことがおすすめです。
【加算の概要】
ひとり親世帯のかかりまし経費(ひとり親世帯がふたり親世帯と同等の生活水準を保つために必要となる費用)を補填するものとして、ひとり親(母子世帯・父子世帯等)に対し支給
(引用元:厚生労働省 【参考資料】生活保護制度の概要等について)
生活保護の支給日は地域ごとで確認が必要

生活保護の受給日は各地域・自治体ごとに異なります。おおよその目安としてはどこの自治体も「1日~5日」の間で入金することが一般的です。
支給日が土日や祝日の場合も、前倒しで入金されるのでその場合でも1日〜5日の間で支給されると考えて良いでしょう。
たとえば、3日が支給日でその日が土曜日の場合、2日に生活保護費が入金されます。
下記でおもな地域の支給日についてまとめているので参考にしてみてください。なお、詳細については最寄りの福祉事務所に問い合わせてみましょう。
おもな地域の生活保護支給日
| 東京23区 | 原則毎月3日 |
|---|---|
| 大阪市 | 原則毎月2日 |
| 横浜市 | 原則毎月4日 |
生活保護のメリット・デメリットを解説
生活保護は経済的に生活が困難である世帯を対象に、必要最低限の生活費を保障してくれる公的な制度です。
たとえ働けなくても最低限の暮らしが保障されるメリットは大きいですが、一方で資産や転居など生活面においてあらゆる制限がかかるデメリットもあります。
ここからは生活保護のメリットとデメリットについて詳しく解説していきます。
税金の援助や、ローン・クレジットカードに関する契約など、生活に重要なことが関わるので、これから生活保護の利用を検討する方はかならず確認しておきましょう。
生活保護のメリット

はじめに、生活保護のメリットについて解説していきます。生活保護を利用するメリットは、おもに以下の2つです。
- 最低限の生活ができる
- 税金や医療費などの援助が受けられる
税金や医療費などの援助は生活の負担を小さくするために重要な要素といえるので、わかりやすく丁寧に解説していきます。
①最低限の生活ができる
生活保護を利用する最大のメリットといえるのが、収入を得られなくても最低限の生活が保障されることです。
厚生労働省は、生活保護について以下のように説明しています。
生活保護制度とは
資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する制度です。(支給される保護費は、地域や世帯の状況によって異なります。)
(引用元:厚生労働省 生活保護制度より)
保有している資産を売却して生活費にあてるなど、できる限りの努力をしても経済的に生活が苦しい世帯を対象に生活保護費が支給されます。
一定の収入を得ている世帯でも、収入が住んでいる地域の最低生活費を超えることがなければ受給可能です。
母(父)子家庭や、障害者の方、同世帯に複数人で住んでいる家庭などでは受給金額が加算されます。
生活保護の受給条件に該当するのかわからない場合は、まずは最寄りの福祉事務所に相談してみましょう。下記表で支給される扶助についてもまとめていますので、参考にしてみてください。
支給される扶助の種類と内容
| 扶助の種類 | 扶助対象となる費用 | 支払内容 |
|---|---|---|
| 生活扶助 | 日常生活に必要な費用 (食費や光熱費など) | 個人的費用と世帯共通費用を合算して算出する。 特定の世帯では加算あり。 |
| 住宅扶助 | アパートなどの家賃 | 定められた範囲内で実費が支給される。 |
| 医療扶助 | 医療サービスの費用 | 費用は医療機関へ直接入金される。(本人負担なし) |
| 教育扶助 | 義務教育を受けるために必要な費用 | 定められた基準額が支給される。 |
| 介護扶助 | 介護サービスの費用 | 費用は介護事業者へ直接入金される。(本人負担なし) |
| 出産扶助 | 出産費用 | 定められた範囲内で実費が支給される。 |
| 生業扶助 | 働くために必要な技能の習得などにかかる費用 | 定められた範囲内で実費が支給される。 |
| 葬祭扶助 | 葬祭の費用 | 定められた範囲内で実費が支給される |
②税金や医療費などの援助が受けられる
生活保護として受給したお金には税金がかかりません。
本来収入を得るときには所得税や相続税、贈与税のように税金が課せられることが一般的ですが、生活保護費は不課税です。
また、住民税も生活保護受給者であれば減免の対象となります。医療費については医療扶助が加算されます。
医療扶助は、病院などで医療サービスを利用するときの経費を補てんするものです。
生活保護受給者は、国民保険の被保険者から除外されるので、医療費の全額が医療扶助として支給されます。
介護サービスについても、本人負担なしで利用できます。税金の免除などについては条件によって異なる場合もあるので、事前に福祉事務所に相談しておくことがおすすめです。
生活保護のデメリット
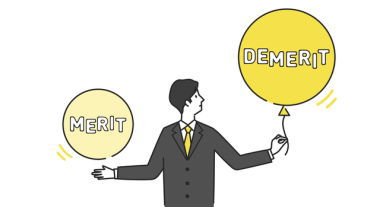
続いて生活保護のデメリットについて解説していきます。
生活保護は最低限の生活が保障される一方で、資産や転居、契約など生活にかかわる多くの制限を受けるデメリットがあります。
おもなデメリットは以下の5つです。
- 資産に制限がかかる
- ローンやクレジットカードが契約できない
- 商品の契約時にもケースワーカーの相談が必要
- ケースワーカーとの定期的な面談を受けなければいけない
- 自由に転居できない
資産に制限がかかる
上記の「生活保護が受けられる人の資産の条件」でも解説している通り、生活保護を受給する場合は保有できる資産に制限がかかります。
貯金、ローンが完済していない住宅や車など、最低限の生活をするにあたって必要のない商品は売却して生活費に補てんすることが優先されます。
あらゆる資産を売却しても経済的に生活が困難な場合、生活保護の受給条件に該当するのです。
ただし、一部保有を認められる資産もあるので、詳しく知りたい場合は最寄りの福祉事務所に相談してみましょう。
ローンやクレジットカードが契約できない
法律上、生活保護を受給しているからといって、ローンやクレジットカードの契約が禁止されているわけではありません。
しかし、厚生労働省はローンを生活保護費返済することを原則認めていないので、無断でローンを組んだりお金を借りることは絶対に避けましょう。
最悪の場合、生活保護の受給がストップされてしまう可能性もあります。借金やローンを返済中に生活保護を申し込みたい場合は、最寄りの福祉事務所に相談しておきましょう。
ケースワーカーと相談の上、クレジットカードについては必要性があると判断された場合契約を認められることがあります。
クレジットカードも、分割払いやリボ払いは借金とみなされる可能性があるので支払いは一括にしておきましょう。
なお、生活保護受給者は支払い能力が低いと判断されやすいので、ローンやクレジットカードの契約が難しい可能性があります。
商品の契約時にもケースワーカーの相談が必要
生活保護受給者は、旅行や贅沢品などの大きな出費をともなう支出があるときにケースワーカーへ相談する必要があります。
自分で稼いだお金であれば、使い道は自由であることが一般的です。しかし、生活保護受給者は生活保護費を自由に利用することは原則認められていません。
もちろん、生活のために必要な出費であれば自由に利用しても問題ありませんが、必要以上に無断で利用すると最悪生活保護の支給を止められてしまう恐れがあります。
下記で詳しく解説しますが、ケースワーカーの面談もあるのでお金の使い道はその都度報告が必要です。大きな出費をともなう商品の契約時は、事前にケースワーカーと相談しておきましょう。
ケースワーカーとの定期的な面談を受けなければいけない
生活保護受給中は、ケースワーカーと定期的な面談をして生活の状況を報告する必要があります。面談の頻度は人によって異なりますが、目安は年に3〜4回程度と考えて良いでしょう。
ただし、1人暮らしをしている支援が必要な高齢者や、生活保護を受給し始めて間もない頃は毎月1回程度ケースワーカーの訪問による面談がおこなわれる可能性があります。
ケースワーカーの訪問は予告される場合もあれば、抜き打ちで訪問に来ることもあるので、常に生活の状況は報告できるよう心がけましょう。
ケースワーカーの訪問による面談の目的は、生活保護受給者の生活面におけるサポートです。きちんと面談のときに受けた指導に従い、自立に向け行動できればメリットともいえます。
しかし、プライバシーの面においては管理されることでストレスに感じることもあるので、その点はデメリットといえるでしょう。
面談でいちばん大切なことは、自分の現状をきちんと理解しありのままをケースワーカーに知らせることです。
生活保護を受給すると自由に転居できない
生活保護受給者は、住む場所の制限を受けます。なぜなら、住宅扶助の金額を超える家賃がかかる住居に住むことが認められていないからです。
また、現在住んでいる住居が生活扶助の金額を超える場合については、福祉事務所より引っ越しをするよう指導を受ける可能性が高いです。
持ち家の場合は、住宅ローンの残債の有無によって対応が変わります。
住宅ローンの残債がある場合、なかには生活保護の対象から外れる場合もありますが、原則生活保護費からのローン返済は認められていません。
下記は、厚生労働省による住宅ローンについての回答です。
Q.住宅ローンがありますが、生活保護を受給することはできますか?
A.住宅ローンがあるために保護を受給できないことはありません。ただし、保護費から住宅 ローンを返済することは、最低限度の生活を保障する生活保護制度の趣旨からは、原則として認められません。
(引用元:厚生労働省 生活保護に関するQ&A)
ローンの残債がない場合、不動産価値が高いなら「リバースモゲージ」など別の制度を利用するよう勧められることがあります。
不動産の価値が低く売却することで住む場所がなくなる場合は、そのまま居住することを認められることもあるようです。
詳細については、最寄りの福祉事務所に直接問い合わせておきましょう。
生活保護受給時によくある質問

最後に、生活保護受給時によくある質問をまとめて回答していきます。
借金があるときの対応や、生活保護費の使いかたに関すること、生活保護の今後についてなどの質問にも回答しています。
はじめて生活保護を受給する方や利用を検討している方だけでなく、現在受給している方にもかかわることなのでぜひ参考にしてください。
- 借金がある状態でも生活保護は受けられますか?
-
借金がある場合でも、生活保護受給の申し込みは可能です。ただし、原則として生活保護費からの借金返済は認められていません。
生活保護費から借金を返済していることがケースワーカーに知られた場合、生活保護を打ち切られる可能性があります。
- 生活保護でもらったお金はギャンブルに使ってもいいのですか?
-
生活保護費をギャンブルのために使用することは原則認められていません。
生活保護費は、最低限の生活を営むために支給されるものです。
生活保護費の使い道は定期的にケースワーカーに報告するので、そのときにギャンブルに使用していることが知られると最悪の場合生活保護を打ち切られる可能性があります。
- 法改正で生活保護受給費が減ると聞きましたが詳細を教えてください
-
「法改正=生活保護費の減少」ということはありません。そもそも生活保護とは、国民の健康で文化的な最低限の生活を保証する制度です。
2025年現在、日本では物価高(インフレ)の状態にあります。今のような情勢のときに生活保護費を減少させることは、国民の最低限の生活を保障できなくさせる可能性があります。
生活保護費は原則5年に1度見直され翌年度に改正されますが、生活保護費が減少する可能性については少ないものの「今後減らない」などの保障はありません。
生活保護受給者も、自分の生活費についてきちんと理解し、法改正の動きには注目しておくべきといえるでしょう。
- アルバイトの給料を隠して生活保護を受けるとバレますか?
-
バレる、バレないということはなく、労働で得た収入については申告しなければいけません。
もしも収入の未申告がバレた場合、生活保護費の返還を求められたり、悪質な場合は刑事告訴されたりすることもありえます。
残念ながら、生活保護費を不正受給している事件は少なくありません。万が一バレたときのリスクを考えると、収入の無申告は妥当ではないでしょう。
- 身内はいますが連絡がつきません。どうすればいいですか?
-
親族や身内に連絡がつかない場合は、扶養意思を認められないので生活保護受給の条件に該当します。
生活保護を申し込むときは、3親等以内の親族に扶養の意思を調査され、扶養の意思がある場合はその扶養に入ることが優先されます。
しかし、扶養の意思がない、連絡がつかないといった理由があれば生活保護の受給が可能です。
また、DV(家庭内暴力)などの事情がある場合は、福祉事務所にあらかじめ相談しておくことで、その親族への連絡は回避できます。
- 将来的には生活保護を受けずに自立したいです!アドバイスをください
-
生活保護の目的は、国民の健康で文化的な最低限の生活を保障することです。
同時に生活保護受給者の自立を支援するものでもあるので、就労の意思があればケースワーカーなどからアドバイスを受けられます。
就労のために必要な技能を習得するための費用を支給する「生業扶助」もあるので、積極的に利用することをおすすめします。
生活保護の条件 まとめ
生活保護とは、国民の健康で文化的な最低限の生活を保障するための制度です。
受給できる条件は限定的で、誰でも受給できるわけではありません。
また、受給したお金は計画的に使い、最低限の生活を守るために使用することを心がけましょう。
収入がなくても最低限の生活ができることが最大のメリットと言える生活保護ですが、その反面普段の生活において制限されるデメリットもあることを知っておきましょう。